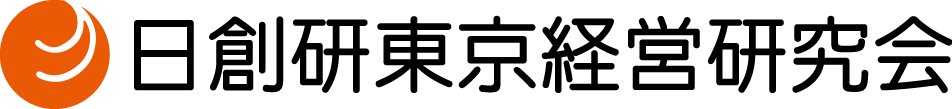今回は日創研のみならず、幅広い分野の講師として大人気の湯ノ口弘二さんに4年ぶりにご登壇いただき、これからの経営のあり方を伺いました。
プロローグ
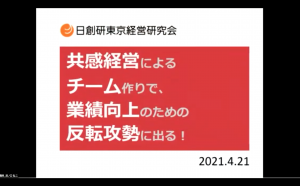
グローバル化された社会、経済活動において重要なのはより多くの情報を集め、分析し時代がどのように進んでいくのかを考えることにあります。
歴史を紐解けば、ヨーロッパの世界進出に始まりアメリカの台頭、さらに新しいイデオロギーの勃興と対立、そして大国となった中国が狙う世界の覇権。
二度の大戦を経て世界の覇権の鍵は経済にあり、経済の鍵である「マネー」の覇権争いが中国とアメリカで起こっています。特に中国は電子マネーによって元をドルに取って代わらせようとしている。
かつては「電子立国」と言われながら今やデジタル後進国となってしまった日本が、現在そこに乗り遅れまいと必死にデジタル化を推し進めているという現状があります。
湯ノ口講師はこういったマクロ経済にもアンテナを張り、その上でミクロな経済、身近な経営に今必要なものは何かを考えていかなければ時代に取り残されてしまう、だからこそ経営者はマクロからミクロを捉えられるよう幅広い情報を積極的に集めなければならないと言います。
その集めた情報をより価値あるものにして経営に反映させていかなければならないわけですが、それはどのようにすれば良いのでしょうか。
より良い経営には経営者の志である経営理念とその「浸透」だとこれまでは言われていましたが、これからは「共感」であると湯ノ口講師は言います。
経営者一人が考え、それを浸透させていくだけでは現在の情報化社会のスピードについていくことはできません。
経営者が考え、それに対して共感が得られれば、社員さん一人一人が考え行動し新しい情報とともに新しいアイデアが膨らんでいく、「全員経営」が実現されるということです。
この「共感経営」こそが会社を一つのチームにし、情報をより価値あるものにして経営に生かしていく、活性化させていくものだということでした。
兆しを読む力を高める
事前の一策は事後の百策に勝る
 今年2021年から電子マネーが世界基準となるであろう2024年の4年間が勝負だと湯ノ口講師は力を込めて訴えました。
今年2021年から電子マネーが世界基準となるであろう2024年の4年間が勝負だと湯ノ口講師は力を込めて訴えました。
特に今年がとても重要だということですが、多くの人が何を考えれば良いのかわからない状態にあるとも言います。
考えられない理由の一つは情報不足であり、先程のマクロ経済の状況をつかみ、世の中の流れを理解した上で予測を立て、自社の経営戦略を打ち立てていかなければいけません。
トップレベルのサーファーが大きな波に乗れるのはトップレベルの技術を持っていることはもちろんですが、天候や海水温や気候といった競技に関わる周辺環境の情報やデータを読み解き「その時」を予測して準備をしているからです。
事業においても技術を磨くことは当然ですが、それだけではうまくいきません。
森信三先生の『修身教授録』にも人との出会いについて「人間は一生のうち逢うべき人には必ず逢える。しかも一瞬早すぎず、一瞬遅すぎない時に…。」とありますが、出会いにもタイミングがあるように、事業でもこの「一瞬早すぎず、一瞬遅すぎない」タイミングが大切だということです。
いくら技術が高くても「世に出るのが早すぎた」という製品もあれば、「あの時出していれば」というものもあります。
「啐啄同時(そったくどうじ)」とは、親鳥が温めている卵から雛が出ようと中から殻をつつく振動に気づいて、親鳥が即座にその卵をつついて孵るのを助ける様から、物事をする時の絶好のタイミングのことを言いますが、人の出会いと同じで一方的な行動だけではなく、それを求めるもう一方の存在と「間」が必要なのだと湯ノ口講師は教えてくれました。
だからこそ、タイミングをつかむためには様々な情報が必要だということ、その情報を得るための高いアンテナを持っていなければならないことがわかります。
さらに、「こんなことがしたい」「こんな世の中にしたい」というゴールが決まっていなければ、どんな情報を得るのが良いかがわからず、結果なんの情報も持たない、取りに行かないということになります。
ソフトバンクの孫正義会長は「まず登る山を決めなさい」と言っています。
登る山が決まれば、その山の高さや環境などに応じた戦略、作戦、準備、トレーニングができる。
登る山が決まっていないのに目標を立てても思うように業績は上がらない。
社員さん、経営幹部、経営者が一緒になって登る山を決めて、一緒になってどのように登るのか作戦を立てるからこそ、それぞれが強みを出し合ってチーム一丸でその山を攻略することができる。
ここで大事なのが、経営者・経営幹部が「なぜこの山に登る必要があるのか」を社員さんに熱く語ることだと湯ノ口講師は言います。
ここが「共感経営」の第一歩だということです。
登りたい山が見えているか
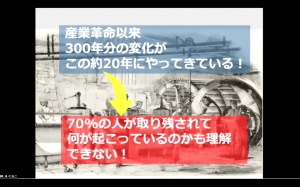 1995年からPHSが普及し始め、その後急速に携帯電話が普及し、それまで一家に1台だった電話が一人1台以上持つようになりました。
1995年からPHSが普及し始め、その後急速に携帯電話が普及し、それまで一家に1台だった電話が一人1台以上持つようになりました。
その13年後にはAppleの「iPhone」が登場し、今やスマートフォンが無くては生活に支障をきたすほどの存在になっています。
ただしAppleは当初携帯電話ではなくiPodという携帯オーディオ機器を作り、音楽データをネット上から取得するという変革を行い、最終形としてスマートフォンというこれまでになかったものを生み出したわけですが、この間わずか8年という早さでした。
Appleのこの偉業には「共感経営」があったと湯ノ口講師は言います。
スティーブ・ジョブズが目指した山に社員が共感し、誰もが同じ山を登りたい、彼が考えるような世の中に変えたいと全員が共感し、達成に向けて全員が行動できたからこそ10年足らずで全く新しい概念の製品を生み出し、社会を変えることができたのだということです。
A.アインシュタインが1905年に提唱した特殊相対性理論、1927年にW.K.ハイゼンベルグが提唱した不確定性原理、これらはいずれも量子力学の理論ですが、この量子力学によってデジタル技術が生み出され、今日のデジタル革命を実現させているということを大半の人は知りません。
その量子力学が将来のデジタル社会を生み出していくことを予見できていた人はいないでしょう。
2020年に起こったこのコロナショックですが、それによって起こっている世界の変化は18世紀に起こった産業革命以来の300年分の変化が凝縮されたものであると湯ノ口講師は言います。
軽工業から重化学工業、そして原子力エネルギーへとつながる技術とエネルギーの開発・発展がここ数十年で劇的に変化し、今コロナ禍にあって革命が起きようとしている。
しかし、その変化を理解できている人は3割ほどで、残り7割の人は今何が起こっているのかがわかっていないといいます。
その理由を湯ノ口講師は明らかに情報不足だと言い、情報を取りに行かない原因が、これから社会がどうなっていくのか、自分はどうなっていきたいのか、つまり「登りたい山」がわかっていないからだと言います。
DX(デジタルトランスフォーメーション)や各種SNSなどに加え、コロナによってこれまで通りのやり方では仕事にならないということを理解し、エッセンシャル企業(必要不可欠なライフラインを維持する仕事をする企業)のように社会から必要とされる企業となるためにはどうすれば良いのかを、時代の流れや兆しを読まなければならないということです。
その上で大切なことが足元の経営環境=ミクロ環境だけではなく、マクロ環境=世界規模での環境分析が必要であり、つまり身の回りのことだけに捉われず、幅広く高所から環境を見て変化の兆しを読まなければならないと湯ノ口講師は言います。
マクロ環境を分析するフレームワークにPEST分析があり、この4つの観点(「Politics(政治)」「Economy(経済)」「Society(社会)」「Technology(技術)」)から見ていくことを勧められました。
変わらなければいけない状況において変われないのは考えるべきことがわかっていないからであり、何をどう考えれば良いかがわからないのは情報を自ら取りに行っていないから。
そして情報を取りに行かないのは「登りたい山」が決まっていないからであり、登りたい山が決まっていないのはつまりコロナによって大きく様変わりした社会において自社が果たすべき役割、解決すべき社会の課題がわかっていないからだと言えます。
今経営者がすべきことは、これまでの事業の立て直しを図りつつ、幅広く情報を集めて分析し、新しい社会的課題に対して自社が果たすべき役割の「再定義」を図ること、そしてその先にある「登りたい山」を定めて全社一丸となって前に進むことであるということでした。
ポスト・コロナ時代の潮流
自社の再定義を図る上で、今起こっていること、起こりつつあることを湯ノ口講師が教えてくれました。
潮流1 デジタル化の推進
 コロナによって急速に広がっているDX、つまりデジタル化ですが、これは世界において日本が遅れをとっていることによって国をあげて取り組み出しているからに他なりません。
コロナによって急速に広がっているDX、つまりデジタル化ですが、これは世界において日本が遅れをとっていることによって国をあげて取り組み出しているからに他なりません。
日本全国、すべての国民の情報を国が管理しようとする法案が可決されることによって「個人情報がなくなる」と湯ノ口講師は断言しました。
これはとてもシビアな問題のように思われますが、個人情報における課題は運用の透明性とセキュリティであり、ここでそれを取り上げません。
デジタル化が進み、国民が高度にデータ管理されている国、特に北欧においては10年以上前からデジタル化に取り組み、それによって高度な福祉サービスの提供に成功しています。
つまり、現在日本のみならず世界で推進されているデジタル化の目的は、少子高齢化といった将来の環境変化に柔軟に対応できるようにするため、公共サービスの効率化・適正化とそれによる国の生産力を高め、国際競争力を高めるためなのです。
さらに、企業レベルにおいてもデジタル技術によってグローバル化が進み、マーケットは世界に広がっていますが、これは単に規模の広がりだけを意味しているのではなく、取引のルールも否応なしに巻き込まれてしまうことを意味しています。
近年電子決済が急速に普及し、コロナによって現金の取り扱いが益々減っていくことが予想されますが、ネット通販においてはカードによる電子決済が基本であり、ポスト・コロナにおいて電子決済をはじめとしてデジタルに対応できていない企業は生き残れません。
また、コロナによって接触機会が減っている中で不可欠になってきているのがオンラインによる「つながり」です。
テレビ会議技術によって離れていても、直接会えなくてもコミュニケーションが取れることで、より効率的で生産性の高い取り組みが実現できることがわかってきました。
湯ノ口講師は「技術進歩は逆戻りしない」と言い、ポスト・コロナにおいてもこのオンライン、デジタルによるコミュニケーションが元に戻るのではなく、より進化した形になっていき、進化させたものが生き残っていくということでした。
潮流2 東京一極集中の見直し
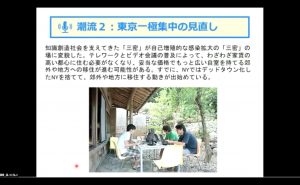 湯ノ口講師のご自宅は香川県にあり、東京にはマンションを借りてそこから職場に行かれています。
湯ノ口講師のご自宅は香川県にあり、東京にはマンションを借りてそこから職場に行かれています。
香川でも今多くのビルが建っているということですが、コロナ前から大手企業でも研究開発部門などを地方に移す動きがありました。
大手企業が東京から地方へ移動あるいは分散する理由は、大都市圏での災害に対するリスクヘッジや家賃や土地代といったコストカットなどがありますが、近年はそれに加えて働く人の生活環境、特に子育て世代の支援とそれに対するロイヤリティの向上、生産性の向上があります。
託児所など首都圏では難しい施設などの環境も地方であれば比較的整えやすく、また自治体の協力もある。
働く側にとっても子育てと仕事の両立は大きな課題であり、企業側にとっても働き続けてもらうことのメリットは大きい。
一方で「働き方改革」によってワークライフバランスについて企業と働く側が試行錯誤していましたが、コロナによって強制的に働き方を変えざるを得なくなり、特に首都圏における仕事において大きく変わる局面を迎えました。
人との接触、「密」を避けるため首都圏に勤める多くの人がオンラインで自宅から会社にアクセスして仕事をするという経験をしました。
これは、技術によって働き方は変えられることを意味していると同時に、大手企業でなくても郊外へ、あるいは地方での勤務が可能であることを示唆しています。
実際IT企業ではすでに首都圏のオフィスを大幅に縮小し、大半が自宅で仕事をするというスタイルに変わっているところもあります。
このようにポスト・コロナにおいてはこれまでのような「東京一極集中」から分散の傾向が続いていくことが予想されるということです。
潮流3 グローバル化の見直し
 コロナ発生前から中国のコスト高によって、ベトナムやタイなど中国に代わる国での生産・供給体制が構築され始めていましたが、コロナによってグローバル化にリスクがあることを知らされました。
コロナ発生前から中国のコスト高によって、ベトナムやタイなど中国に代わる国での生産・供給体制が構築され始めていましたが、コロナによってグローバル化にリスクがあることを知らされました。
ポスト・コロナにおいてグローバル化したサプライチェーンが一度に変わることはありませんが、コロナのようなパンデミックに対するリスクヘッジが求められ、そのための見直しが図られることは間違いありません。
特にコロナの影響で需給バランスが崩れ、ポスト・コロナにおいても問題視されているのが物流の「コンテナ不足」です。
コンテナ不足の理由はコロナによるアメリカをはじめとする急激な「巣ごもり需要」の拡大です。
需要が急激に増えたことで、アメリカの港にコンテナ船が押し寄せ、港の荷捌きのキャパシティを超えてしまった。
その結果、荷を下ろせない船が大量に滞留することになり、空のコンテナが不足するという事態になっているのです。
これは当然運賃の高騰を招き、いずれ製品に跳ね返ってくることになります。
物の値段が上がれば、企業だけでなく家計にも影響を及ぼし経済全体が停滞することにもつながります。
ポスト・コロナにおいては競争力やマーケットだけでグローバル化を考えるのではなく、世界全体の経済動向にも目を向け、各企業がグローバル化のリスクヘッジを考えておかなければならないということです。
潮流4 消費者のプロシューマー化
 これまではDIYや趣味といった個人レベルの手仕事、手作業が社会環境や技術の進化によってプロ化、つまり生産・創造するようになることを「プロシューマー化」と言います。
これまではDIYや趣味といった個人レベルの手仕事、手作業が社会環境や技術の進化によってプロ化、つまり生産・創造するようになることを「プロシューマー化」と言います。
これはプロデューサー(生産者)とコンシューマ(消費者)を重なり合わせた造語で、未来学者のA .トフラーが著書の『第三の波』で用いた言葉です。
この第三の波とは、第一の波(農業化)、第二の波(工業化)に続くものとして「情報化」を指しています。
パソコンやインターネットによって情報が限られた人のものではなく、誰でも収集することができるようになり、さらに個人間の繋がりが容易かつ複雑なことでも簡単に行えるようになりました。
プロが使うような工具を専門店で購入して犬小屋どころか自分の家を建てる人、プロが使うような機材でプロ顔負けの作品をSNSで公開するアマチュアカメラマン、ペットの動画を上手に編集してSNSで公開し大勢のファンを獲得して仕事以外で多額の収入を得る人など、たくさんのプロシューマーがいます。
ネットでの個人売買は当たり前となり、資金調達も可能。
コロナ前から活性化していたプロシューマー化ですが、コロナによってより顕在化されました。
オンラインで仕事をし、ネットで情報を収集し、オンラインでのコミュニケーションが図られました。
ポスト・コロナにおいてこのプロシューマー化もより活性化していくことが考えられますが、湯ノ口講師は企業におけるポイントとして「単価を上げる」ことだと言います。
これはこれまでと同じ物の値段を上げるということではなく、高額な物でもプロシューマーにとって価値ある物であれば喜ばれる。
このとき大事なことは、価値ある物だということが伝わる「ストーリー性」です。
そのストーリーに共感することで、その物の自分にとっての価値に気づきファンになってくれるということです。
潮流5 SDGsの加速
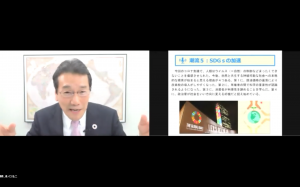 トヨタは2025年の稼働を目標に静岡県裾野市の工場跡地にスマートシティ「Woven City」の建設に入りました。
トヨタは2025年の稼働を目標に静岡県裾野市の工場跡地にスマートシティ「Woven City」の建設に入りました。
スマートシティとは「テクノロジーで課題解決を図る持続可能な都市」のことで、端的に言うとコンピュータで管理しAIで全体最適化を図り続ける街ということです。
持続可能な社会と聞くと真っ先にCO2削減が浮かび、電気自動車が走る姿が思い浮かびますが、今使用しているエネルギーを全く別のものにする(ガソリン車から電気自動車)というよりも、無駄な使用をなくし再生利用できる仕組みによって過不足のない最適な社会活動にしていくかであり、トヨタはその社会の実現に向けて自動車を含めた街全体(空間)を構想しています。
トヨタはこのスマートシティをはじめ「SDGsに本気で取り組む」ために数々のプロジェクトを立ち上げています。
SDGsの実現のためには世界のリーダー、特に経済界の取り組みが不可欠であり、消費者の関心も高いことから「SDGsは経済の戦略」と湯ノ口講師は言います。
大手企業にとっては課題でもありますが、中小企業にとっても社会全体が変革を求めていることなので変われるチャンスであり「ビッグウェーブ」だということです。
潮流6 ローカル型経済の見直し
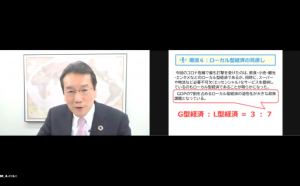 製造業やIT産業を中心とする地域や国境に関係なく展開する経済圏を「グローバル経済圏(Gの世界)」、限られた地域や国でのみ展開する経済圏を「ローカル経済圏(Lの世界)」と言います。
製造業やIT産業を中心とする地域や国境に関係なく展開する経済圏を「グローバル経済圏(Gの世界)」、限られた地域や国でのみ展開する経済圏を「ローカル経済圏(Lの世界)」と言います。
「Gの世界」では、いわゆるグローバル企業の中での競争なので大手企業の中でもトップクラスでなければ生き残れません。
一方「Lの世界」では、同じ地域・商圏でなければ競争自体発生することはありません。
青森県と鹿児県の路線バス会社が競合関係になることはありませんし、同じ東京都内であっても池袋にある商店街の中の雑貨店と日野市の住宅街にある雑貨店にはそれぞれ別の顧客がつきます。
Lの世界の企業は、へたにグローバルに拡大・拡散するよりも、地域における顧客との密着度合いを高めるべきであることがわかります。
そして日本のGDPの7割を占めるのがこの「ローカル型経済」であり、今回のコロナによって大きな打撃を受けたのも飲食店や観光業といった「ローカル型産業」でした。
ただ、コロナによって人々の行動が制限される中で大きな役割を果たしたのも生活圏内にあるスーパーやドラッグストアなどのローカル型産業です。
さらに、人との接触を減らし「密」を避けるために、都心の企業ではリモートワークが推奨され、多くの企業でオンライン会議などが行われることで郊外や地方で働くことのメリットが浮き彫りとなりました。
つまり、ポスト・コロナを左右するのはローカル型経済の復活にあると同時に、ローカル型経済の構造やあり方を見直す転機でもあるということです。
ローカル型産業の多くは労働集約型であり、一番の課題は生産性の向上です。
このローカル型産業の生産性向上の鍵を握るのがデジタル革命における「CからSの世界(への移行)」だと湯ノ口講師は言います。
「デジタル革命」とはコンピュータが一般的に使用されるようになってから起こった出来事ですが、現在は第3期に入っていると言われています。
第1期はコンピューター産業のダウンサイジングで、IBMが衰退しマイクロソフトとインテルが台頭し、第2期はインターネットとモバイルの時代で、その覇者はグーグルやフェイスブックです。
そして第3期としてAIとIoTの時代を迎えています。
ここでポイントとなるのが第2期までのデジタル革命はサイバーの領域(画面上、バーチャル)で起こっており(Cの世界)、カジュアル、つまり人命に関わらないレベルのもので、現在の第3期では人命に関わるレベル、つまりシリアスなレベルの革新(Sの世界)だということです。
これまではインターネットが繋がらなくなっても人が死ぬというほどの問題は起こりませんでしたが、医療の現場や自動運転などの技術は間違えると死ぬ人が出てきます。
Cの世界ではアイデアと早さの勝負で、新しい会社がどんどん出てきて、問題があっても走りながら改善していけば良い、という状況でした。
ところが今後デジタル化が具体的な生活の場、Sの世界にまで及ぶとなると問題が起こってからでは手遅れです。
つまり、これからのデジタル革命はアイデアや勢いだけでは進まず、確かな技術と品質、信頼性が求められるということです。
これまで日本はデジタルの分野で後塵を拝してきましたが、それはこれまでのCの世界においてのことだと言えます。
日本のものづくりに対する考え方、姿勢はSの世界に求められるものであり、それぞれの企業で蓄積されてきたものです。
すなわち、日本経済復活の鍵はローカル型産業とSの世界でのデジタル革命にあると湯ノ口講師は言います。
労働集約型が多いローカル型産業がSの世界でのデジタル革命を推進することで、知識集約型で生産性の高い産業へと変貌していく、今がその時機、タイミングなのだということです。
では、労働集約型のローカル型産業が如何にすれば知識集約型の産業へと変われるのでしょうか?
その一つがDX(デジタル・トランスフォーメーション)であり、事業のデジタル化を図ることにあります。
例えばあらゆる取引場面においてキャッシュレスにすること。
労働集約型のローカル型産業の特徴は生産性が低いことから賃金が低く、慢性的な人手不足になっています。
だからこそデジタル化によって人手不足を補い、生産効率を高める必要があります。
人手がかかるところをデジタル化によって最低限の人員でカバーするだけでなく、キャッシュレスにすることで取引相手に作業を委ねる(決まったところに費用を入れる、届ける)こともできます。
自社事業のDXを推進することが生産効率を高めることになるだけでなく、顧客の利便性を高めることにも繋がります。
特にコロナによって人や物との非接触が大きな課題となっていますが、非接触でもこれまでと変わらないサービスや安心を与えられるということは現在の顧客にとって大きなメリットです。
つまり、自社事業におけるDXを生産効率のためだけでなく、顧客に対する新しい利便性の創造として考えることが重要なのです。
イノベーションチームを育てる
 そしてそれを可能にするのが共感経営であると湯ノ口講師は言います。
そしてそれを可能にするのが共感経営であると湯ノ口講師は言います。
共感経営とは「分析や理論ありき」ではなく、そこにどう言う意味があるのかを問う「意味づけ」と「現場・現実・現物」つまり実践に則した経営です。
競争に勝つため市場を分析し、数量化して科学的な視点から経営戦略を導き出すというのが近年の主流ですが、そこには経験や感性といった人間的な価値観が忘れ去られています。
本来は経験や感性によって意味づけや価値づけがされ(暗黙知)、それを科学とするために数的に変換されたもの(形式知)によって経営されなければなりません。
これらが相互に作用することで知識は増幅し、高度な知恵を生み出していきます。
現場・現実・現物における実践から暗黙知を獲得し、様々な形式知を組み合わせて理論やストーリーを構築していくということです。
ではこの現場・現実・現物における実践からどのように暗黙知を獲得するのか。
それが「共感」を軸にしたコミュニケーションだということです。
共感というのは一般的に「あるある」「それ、わかる」といった相手に同調することだと考えられていますが、本質は「相手の立場に立って、自分ごととして捉える」ことです。
現場で働く社員さんは日々顧客とコミュニケーションを図っていますが、共感力が高い人財、すなわち顧客が必要としているものや抱えている問題を自分ごととして捉えられる人は、より多くの暗黙知を獲得することができます。
しかし、いくら共感力の高い社員さんがいても、その上司やリーダーの共感力が低ければ、現場の暗黙知を組織として活かせないため何の変化もおきません。
暗黙知とはいわば一人一人の主観ですから、そのままだとそれぞれの経験体験から得た「個人知」でしかありません。
それが複数の人との対話によって客観視されることで知識は増幅され新しいコンセプトになり、組織の中で形式知として共有される。
それに様々な形式知が組み合わされて生み出された理論やストーリーが「組織知」となるのです。
そしてここにデジタルやAIによる新たな知が加わることでイノベーションが生まれるということです。
だからこそ、経営者は社員さん一人一人の話を、多くの人の話を聴かないといけない、新入社員だから、若いからというのではなく、若いからこそ最新のデジタル事情についての話を聴かないといけないと湯ノ口講師は言います。
ただし、話を聴けば共感経営は実現するのかというと、そうではありません。
重要なのは「持続的な知識創造の取り組み」にすることであり、個人知から組織知が創造され、それがさらに現場で実践されることによって新たな知識を得る、というサイクルができなければいけないということです。
このサイクルを作るには経営者、経営幹部のリーダーシップが不可欠です。
リーダーがこのサイクルに働きかけ、新しい組織知を生み出していくことでメンバー一人一人のモチベーションが高まり、さらに活性化していくからです。
そのためにも経営トップが「登りたい山」を決め、現場・現実・現物を正確に把握し、話を聴くことで共感し暗黙知を得る。
そこで得た知識を対話を通して新しいコンセプトにまとめ、ストーリーを作り上げて実現させる。
実現し実践されたものは組織知として広く現場で実践され、顧客とのコミュニケーションを通して一人一人が新たな暗黙知を得て、さらに本質に迫ったコンセプトが生み出されていきます。
このサイクルにデジタルやAIの知がレバレッジとなってイノベーションが起こるということです。
ポスト・コロナ復活の鍵はローカル型産業におけるSの世界でのデジタル革命でしたが、それは共感経営による知識のスパイラルアップによって実現できるということがわかりました。
そして、この共感経営による知識のスパイラルアップを実践するチームを作ることが、コロナ禍である今だからこそ求められていることだと教わりました。
湯ノ口弘二講師、貴重な情報とお話をありがとうございました。
ご参加いただいた皆様にも改めて感謝申し上げます。