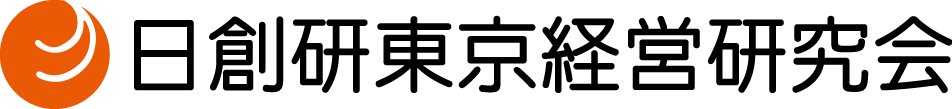今回は「仲間は財産」というテーマで、東京経営研究会の会員企業の中からコロナ禍においても積極的に新しい事業を始められた4社の代表に登壇いただき、事業の概要とその思いについて語っていただきました。
クライアントのための最高の服づくりー株式会社マルチョウ
1社目は墨田区でアパレルの製造業を営む株式会社マルチョウさん。
マイクに向かった代表取締役の長谷川剛さんは冒頭に、このコロナ禍によって22年ぶりの赤字となったことを伝えられました。
しかし長谷川さんは、そんなピンチだからこそコロナ前から挑戦しようと考えていた事業をすべて前倒して実行することにしました。
マルチョウさんは長年大手アパレルブランドへのOEMとして、国産にこだわった高い縫製技術をウリに活躍されてきました。これに加えて近年ODM、さらに独自のブランド事業を展開しています。
1954年の創業以来68年間は国産アパレルの正に「王道」を貫いてきたマルチョウさんですが、その間に様々な社会情勢の変化に伴った局面に遭遇してきました。
最も影響を受けたのが、バブル崩壊の後急激に中国生産による低価格低品質の「ファストファッション」の到来でした。
とにかく費用を抑えるために同じような服が大量に出回ることになり、ニーズとの乖離から需給バランスは崩れてアパレル業界は縮小し続ける状態に陥ってしまいました。
現在の国内の衣料品自給率はわずか2.4%という瀕死の状態にあります。
これに憂慮した長谷川さんは国内に点在する工場を束ね、「メイド・イン・ジャパン」の復活と発展を目的にグループ自社工場「MRUCHO-WORKS」を新設しました。
ただ束ねてスケールメリットを出すというのではなく、各工場の得意技術をさらに高めるために投資をし、各工場で生み出される製品の価値を高めるよう取り組みました。
結果として、業界トップの縫製技術を持った企業として価格競争の激しいアパレル業界を生き抜き、マルチョウさんのOEM事業は安泰かと思われました。
コロナウイルスの蔓延はそんな中突然起こり、緊急事態宣言以降先が見えないコロナ禍に世界が巻き込まれてしまいました。
行動制限がかけられることで市場の停滞感が広がり、生産体制は縮小あるいは廃業という状況に追い込まれていきました。
供給先がストップあるいはブランド廃止ということが起こり、OEM中心のマルチョウさんにとっても死活問題であり、長谷川さんはOEM事業の限界を感じました。
そこでマルチョウさんではアパレルに依存しない新しいビジネスモデルの構築、コロナ禍のように外部環境に左右されない独自のモノづくりを目指すことにしました。それがOEMからODMへの進展でした。
OEM(Original Equipment Manufacturer)とは製造委託であり、相手先のブランド商品を与えられた条件(上代)の中で製造するというもの。これはつまり商品の価値は相手先が決めるというものです。
一方ODM(Original Design Manufacturing)とは開発・デザイン・製造委託であり、相手先のブランドとして販売しますが開発段階から製造元で行うので、商品の価値は作り手がきめるというものです。
現在の状況下だけでなく、この先の時代を捉えて環境に左右される事のない価値の高い商品を作るために、マルチョウさんはOEMからODMへと事業を拡大することにしました。
マルチョウさんは実はここに収益構造の転換という目的の他に、より顧客にとっての価値を高めるための狙いがありました。
現在のアパレル市場は収益確保のための安価生産を求めて、ハイブランドもファストファッションも同じ縫製技術で製造されています。
マルチョウさんでは日本独自のより高度な縫製技術を持っているにも関わらず、OEMではコスト面の制約からそれが市場に出回ることはありませんでした。
「メイド・イン・ジャパン」復活への思いを強く持ち続けていた長谷川さんは、このコロナ禍による市場の閉塞感を打破できるのは日本の高度な技術しかないと思い至り、事業拡大への舵を切りました。
ODM事業を始めるにあたってマルチョウさんがまず始めたのが「自社の眠っている強みを掘り起こす」ことでした。
OEM事業の陰で強みとして世に出すことはなかったけれども、長年の取り組みの中で培われ、他では誰も見たことがない技術を掘り起こしていきました。
OEMとしてのマルチョウの評価は「ノーと言わない」というもので、顧客の要望を100%叶えるために高い縫製技術を磨き、さらに標準のミシンを改造して要望通りに仕上げるという徹底したものでした。
そこで長谷川さんはこの改造ミシンを使った、独自の縫製技術による商品を作ることを考え、社内のメンバーに投げかけました。
社内の大半は反対で、その理由が改造ミシンは1台だけなので量産できない、あるいは商品が限定されることで値段が上がるので売れない、という至極当たり前のものでした。
そんな折、あるアパレル業界の展示会に出品する機会を得たマルチョウさんは、思い切ってその特殊な縫製技術で作られた製品を出品することにしました。
結果は大成功、製品を見た人すべてが「こんな製品初めて見た」「どうやって作るのか」といった驚きと共に大変な評価を受けました。これを受けてマルチョウさんは一気に走り出しました。

世界でマルチョウさんにしかできない技術として4つの縫製技術に名称をつけ特許を取得、専用のミシンの台数を増やし量産できる体制を整えました。
いずれも洋服の「着心地」がこれまでとは全く異なるものとなる技術で、これまでの洋服に対する価値観を一変させるというものです。
この技術を最高の素材とトップディレクターやトップデザイナーによって商品化することで、これまでにない最高の洋服を作ることにしました。
マルチョウさんはこの取り組みで、ファストファッションの流行で同質化し「どれも同じ」「着たい洋服がない」となっていたたアパレル市場を変えていこうとしています。
このマルチョウさんの新しい企画商品は数多くのトップブランドで採用され、さらに世界へ飛び出していこうとしています。
マルチョウさんが取り組んでいるのはOEMからODMへの事業拡張だけにはとどまりません。
そもそもがアパレル依存からの脱却であり、このODMによるファクトリーブランドの先に、オリジナルブランドというゴールがあります。
長谷川さんは先日もこのオリジナルブランドの商品を持って初めてのテレビ通販番組に出演し、見事完売させることに成功し、来年にも新しいブランドが立ち上がる予定になっています。
本来ならOEM企業が同じ市場でオリジナルブランドを立ち上げるのは難しいことなのですが、マルチョウさんのアパレル業界を何とかしたい、日本の高い技術を世界に広めたいという強い信念がクライアントを動かしました。
居酒屋からはじめる魚屋ー株式会社セカンドダイニング
2社目は寿司居酒屋、海鮮酒場を展開されている株式会社セカンドダイニングの早津茂久さんです。
創業54年、早津さんが2代目で創業当時は食料品店として始まりました。
今回の発表では新事業である「居酒屋からはじめる魚屋」について話してくれました。
早津さんは、コロナによる飲食店の営業自粛のが出された時お店をやめることも考えたと正直に話しました。
多くの飲食店が借金をして営業している中、セカンドダイニングさんは無借金経営を続けていたため、お店をやめてコロナが落ち着いたところで再スタートするというのも一つの選択肢として考えることができました。
でも、やめてしまうと社員さんが路頭に迷うことになり、再スタートしたとしても戻ってくるのは難しい。
早津さんにとって無借金経営というのは大きな強みであったので会社を変えずにという思いがありましたが、社員さんのことを考えて借金をしてでもお店を存続させることにしました。
ただ、営業を継続させるとしても、コロナによってこれまでと同じスタイルでやっていけるのかが問題でした。
飲食業界でも特にアルコールについてはコロナ禍で悪いイメージがついてしまったり、リモートワークの影響で会社に来ない、出社しても早い時間に帰宅するというスタイルが広がったことでコロナ前の水準に戻らないと言われています(以前の3割減とも)。
そこで改めてセカンドダイニングさんは自社の強みについて、これからの需要について考えることにしました。
他の居酒屋との違いを考えた時、まず寿司が握れて提供できることが第一に上がりました。同時に新鮮な魚を提供するために独自の仕入ルートを持っていることも上がりました。
他のお店やスーパーなどで売られている魚は市場で仕入れるのが一般的で、東京であれば豊洲市場に仕入れに行きますが、セカンドダイニングさんでは千葉や神奈川の漁港で当日朝に水揚げされた魚を仕入れます。
さらに、この「新鮮さ」がダイレクトに伝える術を理解する出来事がコロナ前にありました。
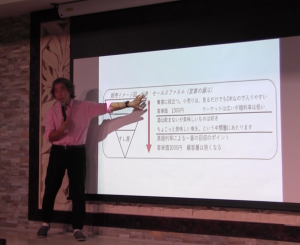 コロナの直前に一部のお店を少し改装したところ、売上が大きく跳ね上がりました。
コロナの直前に一部のお店を少し改装したところ、売上が大きく跳ね上がりました。
それ以前は新鮮な魚を店内で見せていたのですが、改装後にお店の前で見せることにしたのです。
それまではいくら「朝獲れ」の「新鮮な」魚であることを訴求しても売上に結び付かなかったのですが、お店の中だけでなく店頭で魚を見せたところ売上が伸びた。
言葉や画像ではどうしても2次的になることで刺激が弱く伝わりにくかったのですが、例えば生きたイカが店頭で泳いでいたら「新鮮さ」は正に一目瞭然で伝わるということです。
このコロナ前の経験から、商売をするには考えたことだけをやるのではなく、お客さんの脳を刺激するような演出や取り組みも必要であることを実感したと早津さんは言います。
これらのことからセカンドダイニングさんでは「魚屋さんがやっている寿司屋」という新しい事業を始めることにしました。
アルコールがメインの居酒屋ではなく、新鮮で美味しい魚が食べたい人に向けたお店であり、その場で新鮮な魚の寿司も食べられる居酒屋。
そこにはこれまで自分達の仕事を支えてくれた漁師さんの力になりたいという思いもあります。
でも、早津さんの中で一番実現したいのは、また無借金経営に戻すことだと言います。
コロナ前に戻すことはできなくても、コロナで失いかけた自信を、以前の自分達を取り戻したい、そんな思いで始める新事業だということでした。
人材紹介業への挑戦ーNTSグループ
笠原智久さんが勤めるNTSさんは倉庫の仕分けから配送を行なっている運送会社ですが、社会問題を解決する企画を全員参加のプロジェクトとし、社内の活性化と同時に業績向上のための新事業を開発することにしました。
すでにいくつかの事業が進められているということですが、今回は「ドライバー紹介事業」について話してもらいました。
 昨今の人手不足の問題は運送会社でも深刻で、ドライバーはいつもどの会社でも不足している状況です。
昨今の人手不足の問題は運送会社でも深刻で、ドライバーはいつもどの会社でも不足している状況です。
求人広告では思うように集まらないため、現在は派遣会社から運送経験のある人を派遣してもらうところが多いということです。
ただ、派遣会社は単にトラックの運転経験があるという人を紹介してくるため、運送会社が求めるレベルの人材には程遠く、結局は入社後に社内の研修指導員のもとで1ヶ月弱の研修をした上で指導員からお墨付きをもらって初めてドライバーとして働けることになるということでした。
それでも派遣会社には一人約30万円という費用を払わなければならず、コストと生産性のアンバランスが大きな課題となっているということです。
これは業界全体の課題でもあり、運送会社に仕事を依頼するクライアント側のニーズでもあります。
クライアントにとって運送業務を依頼する上で一番重視するのは安全性であり、とにかく事故を起こさず安全に運ぶということが求められます。
どのような教育を受けたドライバーが運転しものを運ぶのかを必ず問われると笠原さんは言います。
そこで各社はこのドライバー育成を求められていますが、その方法は会社の規模によってマチマチで、ドライバーもまともに育成された経験がない人が多い。
その点、NTSさんには過去教習所を経営していた「安全運行指導員」という運転を教えるプロがいて、運転する前の心構えからしっかり指導します。
このことを今回のプロジェクトでは改めて自社の強みであることを認識したということでした。
この「ドライバー紹介事業」は、自社のドライバー不足解消のために人を集め育成していくことが基本で、その中で同業への紹介やマッチングを行なっていく予定です。
そのためには安全運行指導員を増やしていかなければならないといった課題がありますが、同業からの期待や将来的にクライアントの選択基準になるよう、業界のレベルアップに貢献できる事業であることは確かです。
繁盛店のテストケースとなるー株式会社ダイヤ冷ケース
太田和隆さんが代表を勤めるダイヤ冷ケースさんは洋菓子業界向けの冷蔵ショーケースを作り続けて50年という会社。
洋菓子店にもチェーン展開している大手の会社もあれば地域密着で頑張っているお店もありますが、ダイヤ冷ケースさんは主に後者の地域密着型店舗をクライアントとしてきました。
洋菓子店で販売される商品は大きくショートケーキに代表される生ケーキとクッキーなどの焼菓子の2種類があります。
さらに、生ケーキもショートケーキなどの小さな個別のケーキである「プチガトー」とクリスマスケーキのような「デコレーションケーキ」に分類されます。
焼菓子も訪問先への「おみやげ」と中元や歳暮などの「ご進物」に分かれます。
洋菓子店のビジネスモデルは、「プチガトーで集客し、バースデーケーキで信頼を築き、焼菓子で利益を上げる」というのが一般的だと太田さんは言います。
人気があるのは生ケーキの方ですが、消費期限が短いので作ってもロスになる確率が高い上に手間もかかります。その点焼菓子は消費期限が比較的長いのでロスなる確率は低い。
また、記念日などで食べられるデコレーションケーキは予約販売が可能なので、プチガトーよりもロスの確率は低いですが、ユーザーからすればいきなり高いバースデーケーキを頼む前にショートケーキを食べて満足と安心感を得たい。
バースデーケーキはそのユーザーの記念日を知ることになり、継続したアプローチも可能で、より高い信頼関係を築くことができます。
ユーザーの大事な人への感謝の気持ちを伝えるモノとして使ってもらえやすくなるということです。
洋菓子店はコロナ以前から苦境を迎えていたと太田さんは言います。大きな要因は「働き方改革」にありました。
いわゆる街の洋菓子店の多くは良くも悪くも「徒弟制」で、給料をもらいながら技術を磨き、いずれは独立するというスタイルがあり、それゆえに「サービス残業」という意識が無く、場合によっては社会保障も加入していないというのが「当たり前」でした。
それが「働き方改革」が提唱されることでこの「当たり前」が通用しなくなり、経営環境が逼迫してしまいました。
それに加えて、大手チェーン店やコンビニスイーツなど大量製造し安く販売するところが市場に進出してきたことでますます環境は悪くなり、地域密着型の洋菓子店は消えていきました。
街の洋菓子店をクライアントとしてきたダイヤ冷ケースさんにとってもこれは大変大きな問題でした。
 そんな中、太田さんは以前あるパーティーでコンビニ大手の顧問の方の講演を聞いてある衝撃を受けました。
そんな中、太田さんは以前あるパーティーでコンビニ大手の顧問の方の講演を聞いてある衝撃を受けました。
これまでお土産やご進物でのお菓子を百貨店で買うという人が多かったが今はそうではなく、「ここでしか買えないもの」を求めているということでした。
以前は百貨店自体がブランドであり、「百貨店(に入っている店)で買った」というのが一つのステータスだったのですが、さまざまな商品やお店が市場に存在し「個性の時代」と言われる現在では、有名店のお菓子であっても他と同じというだけで贈り物としての価値が下がってしまう。
つまりブランドは大手だから作れるものではなく、ユーザーとその時代の価値観に沿っていれば、誰も知らない地方の街の洋菓子店のお菓子の方が高い価値を持つことになるということでした。
同時に「腕のいいパティシエのお店は立地を選ばない」ということを教えられました。
そこで今回ダイヤ冷ケースさんは、街の洋菓子店を活性化させるため「プロモーション事業部」を立ち上げ、ショーケース製造にとどまらず、ユーザーに必要とされる「売り場づくり」の実地研究をしクライアントに伝えていくことにしました。
実際に地方の有名なパティシエがいる洋菓子店さんに修行に行き、新しいオリジナル洋菓子を作り、自社のショーケースを入れた店舗で自ら販売するというものです。
実際の店舗販売を通して、オリジナル洋菓子の売り上げはもちろんですが、売り方や伝え方について実験・研究し、「繁盛店」の作り方をショーケースと共にクライアントに提供することで洋菓子店の活性化に繋げていくということでした。
ダイヤ冷ケースさんにとっても、これからはショーケースだけを作っていくのではなく、クライアントにとっての価値とは何かを社員さんがこの取り組みの中から考える場にしていきたいということでした。
新しい取り組みを発表してくださった4社の皆さん、本当にありがとうございました。
ご参加いただいた会員の皆様にも改めて感謝申し上げます。