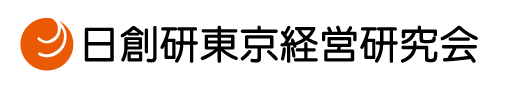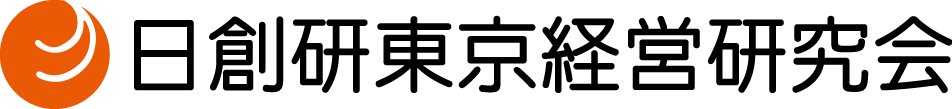「ええな」で受け入れる
松下幸之助翁は会話の中で「悪い」の関西弁である「あかん」とは絶対に言わなかったと金子講師は言います。
「あかん」と言わないといけない状況でも明らかに「ええな」とおっしゃっている。
周囲の人は84歳超えると達観していると言いいますが、金子講師が松下幸之助翁の会話の音声を何度も聞いてみてわかったのは、これは「考え方の癖」だということでした。
これは「言霊」であり、悪い状況を見ても「ええな」と言い切れば全てを受け入れる体制が自分の中につくられます。
普通は「あかんな」と思うと耳を閉じ心を閉じて聞かないし、弾いてしまう。
弾かずになんとしても耳を広げて聞ける体制を作る、これが松下幸之助翁の習性だったということです。
「なぜ成功したのか」を問われた松下幸之助翁は、
「自分は成功してない。そこそこ行ったんわ運がよかったからや」と言い、その後すぐ「素直やったからや」と言い換えられました。
学歴がなかったおかげで、素直な心で衆知を集めることができた。
家が貧しかったおかげで無理なことをすることがなかった。
体が弱かったおかげで、部下に仕事を任せたら部下が育った。
全て「おかげ」という言い方をされていました。
この考え方ができれば「運が良かった」という言い方ができるのですが、それは「素直」だったからこの考え方ができたのであり、だからこそ全てはものの考え方だとおっしゃっています。
素直と感謝は永遠の法則
また、別の塾生から「自分は心配性で寝られないことが多いが、松下幸之助塾主は大成功されているので夜も寝れないことなんてないでしょう」と言われたことがありました。
それに対して松下幸之助翁はこう答えられました。
「いやいや、今でも夜寝れやんよ。飯も喉が通らん時あるよ。だけどな、それがな、リーダーの勤めなんや。夜も寝られんで嫌やと思うんやったらリーダー辞めたらええ。それがリーダーの仕事なんや。それ続くぞ」
ただ、後年松下幸之助翁が不眠症を治していたことがわかったと金子講師は言います。
どのようにして治したか、それは寝る前に「今日1日良かった」「ありがとう」この2つを唱えてもらえればすぐ寝られると言われ、やってみたところ本当に治ったとご本人がおっしゃっていたとのこと。
「良かった」というのは素直つまり「全て良し」ということ。
一日素直だったら全て良し、そしてありがとう、感謝。
これは毎朝「根源の社」でお祈りしているのと同じですが、それを寝る前にもしてみたら治ったということです。
だからこれは「永遠の法則」かもしれないと金子講師は言います。
生きた学びは現場で掴む
何度も出てくる言葉2つ目は「自習自得」です。
松下政経塾にはカリキュラムはありません。
この塾内で研究して、日本国中で研修して欲しいと松下幸之助翁は指示されました。
「国家100年の大計」を練って、それを毎年発表するぐらいのことをやって欲しいとおっしゃった。
塾内には「円卓室」という教室自体が丸く、そこに円卓が置かれた教室があります。
これは講義を受けて聞くという勉強より、周りながらそれぞれが発表し合うことで誰が先生かがわからないようにするためにわざわざ丸い教室にしたということです。
「先生がいない円卓室にして衆知を集めるんや」という言い方をされた。
壁が丸くなった教室ですが、金子講師が建築家の方に見ていただいたところ、四角の教室なら経費的には80分の1ぐらいだと教えてもらいました。
効率を無視してわざわざ部屋を丸くして丸テーブルを入れている、この意図を金子講師は今も調べてる途中だということです。
さらに松下幸之助翁は今の塾生、若い人には足りないことが2つあるとおっしゃった。
1つは日本のことをもっと知って欲しい、日本の良いところを理解してから海外に行って欲しいから、日本人というものをよく研究して欲しいということ。
もう1つは、人間を知っていない、とおっしゃった。
学校では政治学、経営学というのは教えられるけれども、生きた政治学や生きた経営学というのは自習自得で、現場でコツを掴んでくるしかない。
そのコツを掴むには、日本を知ることと人間を知ること、そして現場研修を大事に行ってこいとおっしゃった。
しかし塾生は松下幸之助翁のこの「現場研修優先」に対してほとんどが反対でした。
松下幸之助翁はそんな塾生に「現場研修」の大事さを語られました。
教室で勉強してるだけが勉強ではなく、現場に行って心して見れば万物ことごとく師となる。
本当の経営は中小零細企業の血のにじむような努力を体験しないとわからないし、本当の経営者になれない。
また、そういう血の滲むような中小零細企業の経営者の痛みがわからないような政治家なんか産まない方が良い。
そのために塾を作ったのではない。
中小零細99パーセントそういう方々が日本背負って立っている。
だから、その人たちの痛みがわかるような政治家が生まれないとダメだというのがこの塾の本願だから、その辛酸の一端をなめてこい。
そのための販売店の実習だという言い方をされました。
松下幸之助翁自身が叩き上げで経営をされた、そのご苦労の一部を体験させていただいたらどうかということだと金子講師は言います。
現場で掴んで欲しかった2つのこと
そして松下幸之助翁は販売店に行った塾生から報告と質問を受けられました。
「町の電気屋さんは同じ看板で同じ商品を同じ価格で売って、売れる店と売れない店があるのはなぜでしょうか。塾主だったらどうしたら儲かる小売屋さんができると思いますか」
松下幸之助翁はご自身の答えを言う前に3ヶ月現場研修に行った塾生の答えを聞かせてもらうようにしました。
ほとんどの塾生は学べないと答え、中には販売店に3ヶ月いましたが何も学べませんでしたなんていう者もいました。
これに対して松下幸之助翁は答えました。
「素直な心でな、衆知を集めたらな、必ず繁盛するんや」
「お客さんに対して最大のサービスは聞く力であって、誰か話し方が大事で、技術やスピーチをもっと練習せい、勉強しよう言ってたけど、あれ、技術や。口使わんと耳つこうたほうがええで」
そして、塾生に対して次のように激しく叱責されました。
「小売屋さんっていうのは、無名だけども立派な経営者がいっぱいいて、そんな皆さんのところでお預かりいただいたのに、どうして勉強できなかった。君らには猫に小判やったな。2つのことを掴んできて欲しかっただけだ」
「ひとつは人使い。中小零細企業の皆さんが人使いというのにものすごく苦心されてる。例えば、パートで入ってくれた奥さんの悩み事まで解決しようとしてなかったか。子供さんが受験でね、迷っておられる。お父さんお母さんの介護が厳しい。そんなことまで悩みを聞いて、店主、社長が一緒に解決しようとする姿を見なかったか」
「来てくれた従業員の皆さんが能力を発揮してもらうために社長がどんだけ力を使ってるのか、君はなぜ一緒に生活してわからなかったんだ。人使いっていうのは、1人入れて2人入れて、その分楽になったか。楽になるはずがないんだ。その人の能力を発揮させようとして、いかに心を砕いてるかっていうことをどうして勉強してこなかった」
そしてご自身の体験を語られました。
「自分も町工場として社員募集ってしたけどね、誰も来てくれなかった。来てくれてもすぐ辞めちゃうんだ。だから自分は朝、夜になっておはようございますと従業員来たらね、おはようございますって挨拶運動したんだ。それはやめへんやろなと思って、心配で朝立ったんや。やめへんやろなと思って、明日来てくれたらな、よう来てくれてありがとうで、従業員を迎えてた時代があるんだ」
「松下電器の創業てそうやった。そうやって来てくれと思ってもね、良い人だとこうへん、よそで問題があったような人しかうちにこうへん。だけど、そういう人でも、素直な心になって、良いところを見つけて承認し、褒めて回すして、その人が活躍できる場を作っていく。従業員が成長してもらう。それしか会社の発展ってなかったんだ。それが私のスタートなんや。だから、人使いってのをものすごく大事に考えてる町の電気屋さんの姿をなぜ身近にいてわかんなかったんだ」
もう一つは、少し足を伸ばせば街の電気屋さんを凌ぐ大型量販店がありますが、その量販店に行かないで、なぜ数万円高いここへ来ているのかということについて。
「なぜだと思うんだ。それはね、この店主が学歴があるから、大学出てるからじゃないんだ。お客さんに対してのご要望をしっかり聞いて、お客さんに幸せになってほしい。素直な心で衆知を集めて、素直な心になって、お客さんの幸せを願ってね、熱心に商売されてるからじゃないか。この組織を動かしてるのは社長である、トップである人の熱心、熱意が組織を動かしてるってことをどうして掴んでこないんだ。
「人使いと熱心、熱意がつかめなかったから、この1年間は塾生は無に等しいからみんな落第」
塾生に対する長い公演の中でお叱りになったのはここでした。
中小零細企業の血の滲むような努力を、体験はしたけれども身になっていない、そのことに対してのお叱りでした。
「松下電器は何を作ってる会社ですか」と問われたら、「人を作っている会社です。合わせて電化製品も作っています」という松下幸之助翁の真骨頂は、先ほどの人使いと熱心・熱意にもあったのではないかと金子講師は言います。