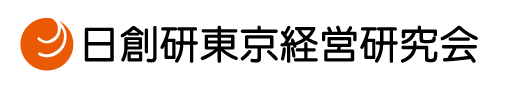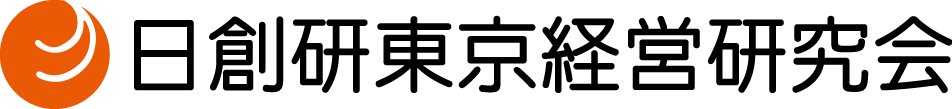闘争の果ての餅つき大会
日本のモータリゼーションが花開く時代、昭和35年(1960)に武蔵境自動車教習所さんは創業しました。
今回の講師である髙橋勇会長は昭和57年に入社しましたが、それまで勤めていた生命保険会社とはまるで違う、あまりに旧態然とした経営に違和感を持ちました。
ただ、当時は教習所があればお客様に来ていただけるという状態で、技能教習の予約を取るために朝5時ごろからお客様が教習所に来られるという、今では考えられない状況でした。
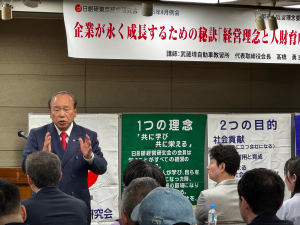 しかし、昭和63年に労働組合が発足すると会社は大きく変化しました。
しかし、昭和63年に労働組合が発足すると会社は大きく変化しました。
翌年の4月1日に初代社長が勇退、その日に2代目社長が就任しますが、労働組合との闘争に苦しんでいたことから翌日に自殺してしまいます。
そんな大変厳しい状況の中、髙橋講師はその日のうちに社長に就任し、経営の立て直しに取り組むことになりました。
それでも労働組合は髙橋講師を吊し上げて、給料のベースアップや待遇など自分たちの権利を声高に主張し続けました。
社長の間ずっとこのままなのかと思い悩んでいたある時、髙橋講師に一つの考えが頭に浮かびました。
「彼らの目線を社長ではなく地域社会に向けさせよう」
教習所が経営できるのは公道を使わせてもらうなど地域社会の支援があるからこそ。
そこに気が付いた髙橋講師は、労働組合執行部の中でも親しい人に声をかけ、就任した年の12月に地域の方を集めて「餅つき大会」を開催しました。
その時はたくさんの人が来ませんでしたが、髙橋講師にとってはやったこと自体、地域の人たちが集まってくれたことが大成功でした。
そして何よりも、髙橋講師の経営者としての方針に気付くことができました。
翌年には第1回サマーフェスティバルを開催しましたが、それらが現在まで続いてそれぞれ36回を数えるに至り、今や地域の風物詩になっています。
この苦しい体験を通して、人間は追い込まれた時に逃げなければ色々アイデアが浮かぶものだ、と髙橋講師は言います。
逃げるからアイデアも浮かばないし、逃げるから後で後悔するのだとも。
現状から逃げなずそこにとどまっていれば、必ず何かできる、何か方法があるということです。
髙橋講師が社長に就任したのが平成元年、平成10年の春闘での団体交渉でようやく決着するに至りました。
10年間闘い続け、現在でも労働組合はありますが現在は協調路線で会社の業績を上げるために協力しています。
理念で変わった会社
髙橋講師は平成5年(1993年)に日創研の研修を受講し、平成6年(1994年)には「共尊共栄」という経営理念を発表しました。
これは「社員さんを幸せにする、お客様を幸せにする、地域社会に貢献する」という意味であることを発表しました。
当時はまだ労働組合でいつも責められていた髙橋講師でしたが、経営理念を発表してからは経営理念に沿った仕事しているかということを労働組合側に問い詰めるようになりました。
同時に社員さんにも学んでもらうために日創研の研修に派遣したところ、多くが辞めていくことになりました。
これは辞めさせることが目的ではなく、社員さんの意識改革が目的でしたが、結果的に毎年20パーセントもの社員さんが辞めていったということです。
一方で客数が増えていることから採用を増やしたところ、毎年新入社員さんが30パーセントを占めることとなり、会社の体制も体質も大きく変化することとなりました。
つまり、経営理念を作り、社員さんに共有して「理念経営」を一緒にやっていこうと言ったところ、会社と対立するような人は辞めていき、「共尊共栄」という理念を共有できる社員さんだけが残り、業績が上がっていったということです。
平成7年(1995年)の35周年の時、東京に教習所が61社がありましたが、その中で武蔵境自動車教習所さんは11位でした。
この時、髙橋講師は40周年、つまり5年後には東京で1番になろうと、ビジョンを掲げて取り組みました。
結果的に、その後2番にしかなりませんでした。
しかし、労働組合と激しくやり合っていた会社が理念経営をしたことによって、「自分たちは何のために仕事しているのか」「自分たちはお客様に何ができるのか」を全社員が真剣に考えたことで業績が上がっていったことは紛れもない事実。
それぞれの会社に理念があるかもしれないが、それが本当に社員さんに浸透しているかどうか。
理念があっても業績が上がらなければ、それは社員さんに浸透していないと髙橋講師は言います。
理念の浸透で安定した業績
 その後、武蔵境自動車教習所さんは令和3年(2021年)には東京で1番になりました。
その後、武蔵境自動車教習所さんは令和3年(2021年)には東京で1番になりました。
ただ、髙橋講師は長らく2位であったことが自慢だと言います。
それはなぜか?
武蔵境自動車教習所さんが2番だった間に1番だった会社が複数あります。
およそ業績というのは山の絵を描くように、頂点まで上がっていきますが長続きすることが難しく、しばらくすると山を下るように業績は下がっていきます。
武蔵境自動車教習所さん東京で2番でしたが、20年間にわたってずっと2番をキープしてきました。
これが理念の力であり、理念が浸透していないと必ず業績は落ち、理念が浸透すると業績は安定すると髙橋講師は言います。
このことが如実に現れたのがコロナ禍でした。
コロナ禍で公共交通機関が使いにくくなったこともあって自家用車の需要が高まり、普通免許や自動二輪免許を求めて自動車教習所はどこも盛況でした。
武蔵境自動車教習所さんも2020年、21年と続けて過去最高の客数を記録し、都内1位全国2位となります。
2022年、23年には若干減りましたが都内1位、全国1位となりました。
これは武蔵境自動車教習所さんだけでなく、ほとんどの自動車教習所が同じようにコロナ禍で数字を伸ばしました。
しかし、2023年でコロナの終息すると同時に、「夢から覚めた」ようにほとんどが元に戻って業績が落ちてしまいました。
そんな中武蔵境自動車教習所さんは元に戻るどころか、さらに上を目指して業績を伸ばし日本一になっています。
でも、髙橋講師は東京で1番、日本で1番になるのは目標であって目的ではないと言います。
目的はあくまで「日本で一番幸せの社員さんを作る」ことだから、まだまだもっと上を目指さなければいけないということでした。
何かあっても絶対に逃げるな
では、なぜ武蔵境自動車教習所さんがコロナ禍を経てもなお業績を伸ばし続けることができたのか。
髙橋講師には忘れられない重い決断と、そこで得た経営者にとって重要な教訓を得たと言います。
2020年8月10日、コロナが急速に拡散し出した頃、武蔵境自動車教習所さんの社員さんがコロナに感染したことがわかりました。
出張で高松に降りた直後に会社から一報を受けた髙橋講師は、そのまますぐに会社へ戻りました。
幹部社員さんを招集し、対応を協議しましたが、心配と不安に覆われてどうにもできません。
なぜなら当時、緊急事態宣言が発令されマスコミだけでなく社会全体が不安に駆られて感染者と感染場所、感染ルートに過剰なまでの反応を示していたからです。
つまり、社内で感染者が出たことがわかれば会社にとって大きなダメージになることが予想されました。
しかし、この時髙橋講師が決断したのは「すべてオープンにしろ」ということでした。
社員さんをはじめ、お客様である教習生、地域社会すべてに一切包み隠さず知らせるよう指示を出しました。
同時に経営研究会の仲間に連絡をして、消毒してくれる会社を紹介してもらうようにし、その日のうちに教習車から館内すべて消毒しました。
次の日の朝からは、会社に感染者が出たことを来る人全員に伝え、周辺地域にも伝えるための書面を配りました。
社員全員が感染者が出たことに対して頭を下げ、消毒等実施している対処対策をすべてお客様に伝えました。
すると、3日後には「武蔵境さんだったら平気ですよ」と言ってくださるお客様が出てきました。
それは、感染者が出たことを公表したのは武蔵境さんだけだから、ということでした。
このことから、「何かあっても絶対に逃げるな」と髙橋講師は言います。
隠すから何も手が出ない、オープンにするから手が打てる、オープンしたからこそお客様から信頼してもらったということでした。
そして、経営者が隠すこと逃げることをした時に一番怖いのはお客様ではなく社員さんであるということも。
社員さんは経営者の判断や行動を黙って見ています。
何か都合の悪いことがあったら隠す、逃げるという経営者を信頼する社員さんはいません。
武蔵境自動車教習所さんは経営計画を全社員に対して発表していますが、その中で会社の財務についてもすべてオープンにしています。
だからこそ、社員さん一人一人が自分の目標に対しても正しく理解し、達成のために自律的に考えて行動しています。
長年経営者が実践し見せてきた取り組みが、コロナ禍のような緊急事態にあっても「即座」に反応することができたということです。
日本一の教習所の人財育成
続いて、武蔵境自動車教習所の幹部社員さんから人財育成についての実践事例を紹介してもらいました。
まず、人材開発部課長の山上沙和子さんから採用についてお話ししてもらいました。
あくまで人と感謝力
 コロナ禍で、何が正しいのか全くわからない状態、今までの常識が何も通用せず、良いだろうと思ってやったことが世の中から批判される、そのような迷いの状態の中で一番指針になったのは「共尊共栄」の理念だったと山上さんは言います。
コロナ禍で、何が正しいのか全くわからない状態、今までの常識が何も通用せず、良いだろうと思ってやったことが世の中から批判される、そのような迷いの状態の中で一番指針になったのは「共尊共栄」の理念だったと山上さんは言います。
周りと助け合い、大切にして、感謝する気持ちを伝えていく。
地域社会の方、お客様が一番求めてることは何かを考え、消毒専属のスタッフを採用して、とにかく清潔を保つといったことを行いました。
また、コロナ禍で武蔵境自動車教習所さんでは色々なものをデジタル化していきました。
教習スケジュールなど紙で出してもらっていたものをウェブ上で出せるようにし、学科教習もオンライン化するなど様々なものをデジタル化していきました。
看板やチラシなどもほとんどやめて、オンライン広告やSEOなどに費用をかけるといった営業戦略でも変化させていきました。
ただ、一方で追求していくと結局は人やアナログの部分は外せないということも実感したと山上さんは言います。
どれだけデジタル化しても、お客様からのアンケートでは「インストラクターが良かった」、「受付スタッフに支えてもらって免許が取れた」といった、「人」が必ずアンケートに出てくる。
だからこそ人財育成の指針でもある「出る杭を伸ばす」という人事理念の下、人を徹底的に育てていくということです。
自分を育てていくということが、理念にある「可能性を育てる」ことになり、「未来のために生きる」ということに繋がるということを感じる機会だったと山上さんは振り返ります。
では、採用について見てくと、先述のコロナ禍での免許取得者数の急増からのコロナ後の急激な減少同様に、採用でも応募が減ってきていると同時に、昨今の風潮で新卒においては待遇面を見るといった傾向はかなり強くなっていると山上さんは言います。
以前はまだ「選ぶ」立場でしたが、現在は学生さんをスカウトしていかないと応募がないなど苦しい状況にあります。
それでも、自分たちの取り組みや地域への貢献、働くことでどのように成長できるかという側面を伝えていくことで、徐々に応募が増えてきているということです。
ただ、そういう状況下でも、いかに「良い人材」を取るかというところを工夫して取り組んでいると言います。
武蔵境自動車教習所さんでは、採用時見ているのは学歴や運転スキルではないということです。
勉強に対してやるべきことをやってきたかという視点で評価はするが、学歴で足切りなどはしない。
教習所だと運転スキルや運転試験があるように思われますが、運転の試験などは取り入れていません。
運転の頻度や違反歴などは聞きますが、そこが採用の決定打になることはほぼないということです。
一番見ているのは「感謝力」だと山上さんは言います。
どれだけ感謝の気持ちを持って日々生活してきたかというところを一番見ているということです。
日々のことに当たり前だと思わず感謝しているというこの「感謝力」は入社後に育てるのは非常に難しい。
でも、それを持っていれば自然と学び、周囲の人と良い関係も結ぶことができます。
このことから、この「感謝力」を採用時に重視しているということです。
では、どのようにしてそれを見るのか、武蔵境自動車教習所さんでは「ありがとう作文」を書いてもらっているということです。
「あなたが今まで生活してきた中で感謝していることを600字から800字で30分で書いてください」
これは原稿用紙2枚分で、1枚半以上は書かないといけないので、書ける人と書けない人が出てきます。
また、作文の書く字が雑で読めない字になる人などがいて、性格が出てくる場合もあるということです。
内容はもちろんですが、基本的には両親への感謝の気持ちがあるかどうか。
もちろん家庭事情はそれぞれあるため強制ではないが、両親に関して色々あったけれども最終的には感謝していますという人が「我が社に、社風に合っている」という考えのもと、外せない条件として見ているということです。
面接など様々行っている中で、面接では出てこない人柄が作文では出てくる、そこにこだわりをもってやっているので作文は絶対全員にやると山上さんは言います。
相手の良いところと自己への客観視
 続けて、営業部長の國領諭史さんからは、武蔵境自動車教習所さんの人財育成の話をしてもらいました。
続けて、営業部長の國領諭史さんからは、武蔵境自動車教習所さんの人財育成の話をしてもらいました。
武蔵境自動車教習所さんの人財育成で一番のメインは、毎日取り組んでいる「朝礼」です。
この朝礼は「アウトプットの場」と「承認の場」であり、お互いを認め合うところをとても大事にしているということです。
それが一番現れているのが、社員同士で良いところお互いに言い合う「褒め褒めリレー」です。
どうしても照れくさいところもありますが、毎日やっていると違和感なくできるようになると國領さんは言います。
毎日行っていると、良いところを褒めよう、良いところを見ようということが習慣になってくるからです。
これはそもそも、教習所の試験が「減点方式」で行われ、いきなり100点の状態から始まり、そこから「確認し忘れ、10点減点」などといって70点切るとその時点で不合格になるという仕組みから、試験管はどうしても思考や見方までもが常に減点方式で見てしまうようになるところから、それを変えるために始められました。
良いところを見て、良いところを伸ばしてく、試験を受けるお客様もその方が絶対に満足して卒業していただけるという思いも込めて、
朝礼では良いところを褒めていくということでした。
また、教習所はお客様がお金を払ってインストラクターに頭を下げて「教わる」というところです。
教習の完了、承認をもらうためにお客様の方がインストラクターに気を使う。
そうすると、次第に偉くなった、立場が上だという風に勘違いするようになる。
これは教習所という狭い世界の中だけで仕事をしているから起こることです。
でも他業種の事例を見ると、苦労していろんな工夫をして1人のお客様を迎え入れたり、価値を生み出そうと努力していることがわかります。
教習所のインストラクターも勘違いがないように、他業種から学びプラスになるようなことを身につけて欲しいということから、毎月1回『理念と経営』の勉強会を行なっているということでした。
みんなで『理念と経営』を読み、お互いの意見をぶつけ合う、ディスカッションで人の意見を聞いて今後の教習に活かすということを行なっているということでした。
また、日創研の可能志向研修を受講して、誰もが前向きで「どうすれば出来るか」という考えで行動できるようにしていると同時に、1人のお客様に対してベテラン、中堅、新人の3人でチームを組んで卒業まで導くということにしているということです。
こうすることで、先輩と後輩双方が教習の進め方や問題点を共有、意見を交わすことでお互いに成長してくことができます。
お互いの行為や発言が理念に沿ったもの、実践になっているかがわかり、お互いに理念が浸透していくということでした。
人との関わりを通して成長を実感
 次に、業務部係長の赤石沢香菜さんから、地域貢献について話してもらいました。
次に、業務部係長の赤石沢香菜さんから、地域貢献について話してもらいました。
武蔵境自動車教習所さんは地域の方々に対してさまざまなイベントや活動をしていますが、これは地域の方々に感謝を伝えると同時に人財育成として行なっていると赤石沢さんは言います。
イベントに携わることで、「免許取れたよ、ありがとうございました」と伝えに来てくださる方もいれば、「こういう風にイベントも活発にやっていて、いつもありがとうございます」など、普段出会えない地域のお客様の声が聞くことで、地域のお客様との関わりや会社が地域の方に支えられていることを実感できます。
また、イベントの実行委員になると先輩にも指示を出していくことになりますが、後輩からの指示に対しても素直に応じ積極的に行動するなど、フォローしてもらうことで後輩のリーダーシップに自信がついていき、それが普段の仕事ぶりに繋がっていきます。
その中で、赤石沢さんからコロナ禍での忘れられないイベントについて教えてもらいました。
コロナ禍では「3密」と言われて大勢が集まるイベントができなくなってしまい、地域の風物詩にもなっていた花火大会も中止を余儀無くされました。
この時、いつもお世話になっている花火職人の方から中止になって花火がたくさん残っていることを聞いた髙橋講師は、地域の方に何も告げずに年末にその花火をあげることにしました。
当然批判されることも考えられる中、届いた一通のメールに武蔵境自動車教習所の社員さんは皆感動しました。
「近隣に住んでおります。本日の花火、全く知らなかったので、大変嬉しいサプライズでした。
19時に破裂音が聞こえ、一瞬事故かと思って自宅のベランダから外を見たら、綺麗な花火が貴社の方向から見え、すぐに教習所からのプレゼントじゃない、と家族で大騒ぎになりました。
同じマンションの人たちも皆歓声の声。
小さなお子さんから大人まで、みんなの歓声がすごかったです。
私は貴所のお心遣いに感動して涙が止まりませんでした。
今年はみんなが様々な場面で我慢を強いられることの多い一年だったと思います。
みんなで頑張ったよねと年末に素敵なプレゼントをいただいたような気がしました。
花火が終わった後、マンションのあちらこちらから、感謝の気持ちから割れんばかりの拍手喝采が自然と湧き起こりました。
本当にありがとうございました。
武蔵野に、武蔵境に貴所のような教習所があってよかったです。
武蔵境、住民みんなみんなの自慢の施設です。
これからもどうぞよろしくお願いいたします。」
多少のクレームもありましたが、このように会社がやることを地域の皆様が応援してくれて、その応援に対して自分たちも感動し、また地域のために、来ていただけるお客様のために頑張ろうとすべての社員さんが強く思えた一通のメールでした。
この花火のように、地域の方や関係会社さんのため行うことで、教習所に対する思いを実感することが人財育成になっていると赤石沢さんは言います。
自分の使命に気づいてビジョンを持て
 最後に髙橋講師から参加者に向けてメッセージが投げかけられました。
最後に髙橋講師から参加者に向けてメッセージが投げかけられました。
世の中がどうであれ、日本の経済がどうであれ、それぞれの業界がどうであれ、それぞれの会社が伸びないといけない。
日本の景気悪い、日本の政治が悪いと言っても何も変わらない。
変えられるのは自分が手の届く範囲であり、そこでとにかく徹底的に変えていくしかない。
やれることはたくさんあり、そう思えばできる。
そのためには明確なビジョンを持つこと。
自分の人生をどう使うかということを明確に持つ。
自分の会社を、社員さんをどうしたいのかということを明確に持てば、必ず方法や手段は出てくる。
それをやるのは経営者だけではなく、社員さんも含めてやる。
だから理念が必要。
夢なき者に理想なし。
理想なき者に計画なし。
計画なき者に実行なし。
実行なき者に成功なし。
故に、夢なき者に成功なし。
これは吉田松陰の名言ですが、髙橋講師はいつもこの言葉を目の前に置いて仕事していると言います。
自分の夢は何なのか、自分の使命は何なのか、どのように世の中に貢献できる会社になるか、世の中に必要とされる会社になるかということを真剣に考えようと投げかけられました。
髙橋勇講師、山上沙和子さん、國領諭史さん、赤石沢香菜さん、貴重なお話しありがとうございました。
また、ご参加の皆様にも改めて感謝申し上げます。