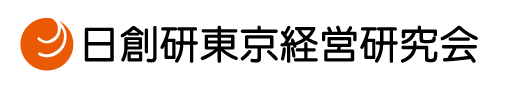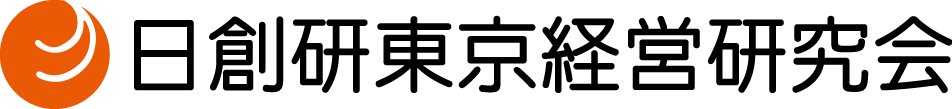2025年7月23日、東京経営研究会7月例会にて、愛媛県で洋菓子専門店を運営する有限会社ラポールの橘憲一郎代表取締役と藤田紫乃取締役にご講演いただきました。
「社内に共感の輪を広げ、会社の永続に繋げよう!」というテーマのもと、6期連続赤字から現在21期目を迎える同社の劇的な組織変革の実体験を通じて、経営における「共感」の重要性について学ばせていただきました。
講師プロフィール〜スターバックスから愛媛へ
 橘憲一郎代表は1999年、スターバックスコーヒーが関西1号店をオープンした頃に入社。
橘憲一郎代表は1999年、スターバックスコーヒーが関西1号店をオープンした頃に入社。
「ピープルビジネス」という言葉に惹かれ、3度の不採用を経て4回目でようやく合格。
池袋明治通り店から始まり、年間120店舗がオープンするペースの中で採用と教育を経験されました。
2005年に地元愛媛に帰郷し、有限会社ラポールを創業。
現在、洋菓子専門店5店舗を運営し、95%が女性スタッフ、約63名と共に21期目を迎えています。
同社では商品をマズローの5段階欲求と照らし合わせ、特に誕生日ケーキは「所属の欲求を満たす、家族の一員で無条件で愛されるお祝いの時間をサポートしている」と位置づけています。
一通の手紙が教えてくれた仕事の真の価値
橘代表のスターバックス時代、常連のお客様「まささん」から5枚にわたる手紙が届きました。
車の整備士になる夢を叶えたものの人間関係に悩み、うつ病を患って故郷に帰った彼が、スターバックスで過ごす時間によって「生きる気力を取り戻した」という感謝の言葉が綴られていました。
「本当にこの皆さんが迎えてくれた空間と、その笑顔であったり、本当にこのコーヒーやさりげない会話が僕の生きる気力を与えてくれました。本当にありがとうございます」
この手紙を読んだ新人の学生スタッフが号泣する姿を見て、橘代表は仕事の真の価値に気づかれました。
数百円の商品を通じて、人の心に活力を与えることができる—この体験が、心と心が繋がり共感・共鳴することを意味する「ラポール」を会社名に込めた理由となったのです。
どん底からの出発〜債務超過3000万円の現実
 しかし創業当初の有限会社ラポールは理想とは程遠い状況でした。
しかし創業当初の有限会社ラポールは理想とは程遠い状況でした。
6期連続赤字、累積債務超過3,000万円、離職率40%(10人入れば4人辞める)、財務格付け最下位の「撤退勧告レベル」という厳しい現実がありました。
橘代表は振り返ります。
「創業の思いでラポールを築こうと思って事業をしたが、全く自分はそれとは真反対のことをしていた。資金繰りや目の前のお金のことばかりが頭に入って、従業員とちゃんと向き合って話も聞けないし、話もできなかった」
転機となったのは2010年の愛媛経営研究会入会でした。
愛媛の先輩であるマルブンの真鍋現会長の「12年連続黒字経営の秘訣〜人を大切にする」という講演に衝撃を受け、「ハンマーで殴られたような思いがあって、途中で後ろの端っこで聞いてたが、悔しさと情けなさで涙が出てきた」と当時を振り返られています。
データが証明する「共感」の力〜やりがい指数アンケート
同社では年2回、無記名で「やりがい指数アンケート」を実施しています。
「あなたは明日職場に行くのが楽しみですか」
「あなたは職場で意見が自由に言えますか」
「あなたは働くことで自分の成長を実感していますか」
を1-10点で評価。このアンケート結果と各店舗の売上対前年比を照合したところ、やりがい指数の高い店舗ほど売上対前年比が高いという明確な相関関係が判明しました。
「明日仕事に行くのが楽しみで仕方ないスタッフばかりで、モチベーション高く仕事に来て、意見も自由に言える。そしてやってみてうまくいったいかなかった、それを通して自分の成長を実感できる。そういう組織になっていれば、お客さんは自然と喜んで業績上がるんだな」と橘代表は分析。
さらに愛媛経営研究会での調査では、「理念と経営の社内勉強会」を実施している46社の黒字率が95.7%という驚異的な数値を示していました。
A4用紙5枚の手紙が起こした組織革命
2018年3月、同社に大きな転機が訪れました。
当時店長だった藤田取締役から、A4用紙5枚にわたる改善提案の手紙が社長に提出されたのです。
繁忙期真っ只中でありながら、現場の疲弊と経営陣との認識のズレを指摘する内容でした。
通常の店長会議を中止し、この手紙について9時間にわたって話し合いを実施。
テレビ局の密着取材も受けながら、組織の課題と真摯に向き合う姿勢を示されました。
藤田取締役は証言します。
「上の人たちは会社を良くしようと思って運営している。下の人たちも会社を良くしたいと思っている。でも、その思いが全く噛み合っていない状況があった。同じ日本語を喋っているのに、話し合いの中でもすれ違う。涙を流しながら話し合って、そこが私の中では大きなターニングポイントになった」
この対話こそが、すべての変化の起点となったのです。
藤田取締役の原体験〜うつ病からの回復と信頼関係
 藤田取締役は19歳の時、大学の春休み中に2ヶ月間アルバイトとして同社で働いた経験がありました。
藤田取締役は19歳の時、大学の春休み中に2ヶ月間アルバイトとして同社で働いた経験がありました。
その後、大学4年生頃からうつ病を発症し、前職を経て再び同社に戻ってきました。
「環境を変えただけじゃ治らなくて、ずっと働きながら泣いていた。情緒がすごい不安定だったが、当時働いていた子や店長さんたちが『大丈夫だよ、大丈夫だよ』と言ってくれた。社長とも閉店後のショウケースの後ろで『ちょっと休みたい』と話したら、社長も涙しながら『俺が代わりに5日間出るから休んでおいで』と言ってくれた」
この体験があったからこそ、A4の手紙を書くことができたと振り返ります。
「私たち店長の共通認識として、社長をはじめ上のメンバーが『どうしてそう思ったの?じゃあどうしたらいいと思う?』と絶対話を聞いてくれるという確信があった。この信頼を作り上げてきたのは、それまでの積み重ねだった」
対話から生まれた具体的改善策
9時間の話し合いを機に、同社は具体的な改善策を実行しました。
まず「タイプ別採用」を導入。リーダーになりたい人、お菓子を作りたい人、接客をしたい人、新事業開発をしたい人というように、求人のページと募集の言葉を分けて明確化しました。
次に「ゆとりを作る」ことを重視。
新しいことをプラスするのではなく、自動充填機・自動包装機を導入して生産性を向上させ、現場の時間を創出しました。
さらに「多様なパートナー構成」として、フルタイムで1日10時間近く働く従来の形から、より細かく求人を出し、女性のライフステージに合わせたサポート体制を整備。産休復帰の際には先輩ママさんが事前面談を行うなどの仕組みも構築しました。
最後に「委員会活動」を通じて、現場主導で商品開発や改善活動に関わる場を一緒に作っていくようになりました。
劇的な成果〜採用から業績まで
これらの取り組みの結果、同社は劇的な変化を遂げました。
採用面では年間応募者数が約90名と大幅に増加し、定着年数も向上(1年で辞める人がほとんどいなくなり、5-6年続く人が増加)しました。
業績面では、本店移転後の売上が287%増を実現。
さらに現場にゆとりができたことで、従来は3日前締切だった誕生日ケーキを当日・前日でも受けるようになり、年間14万個出るチーズケーキには「お疲れ様」などのメッセージを添えるなど、機能的価値にプラスして情緒的価値を現場が自ら提供するようになりました。
橘代表は強調します。
「対話を通した13期以降、この話し合いの中で決断をしていく意思決定で、少しずつ売上、利益が上がっていった。このターニングポイントはこの話し合いでした」
人間力重視の採用・育成〜「鬼と金棒」理論
 同社では「鬼と金棒」の考え方を人材育成に活用しています。
同社では「鬼と金棒」の考え方を人材育成に活用しています。
鬼を人間力(感じる力、考える力、感謝する力)、金棒を技術(ケーキ作りなどの専門技術)と位置づけ、技術は後から学べるが人間力は採用時から重視すべきという方針を採用しています。
14年間継続している「理念研修6ヶ月コース(ラポール研修)」では、難病を抱える子どもたちへのお菓子教室、夢ケーキプロジェクト(子どもの夢をケーキで表現)、社内理念体験の事例集作成、障がい者支援施設との連携などを実施。
特に印象的なのは「オリジナルインターンシップ」で、特別なプログラムを用意するのではなく、店舗オープン時の上棟式参加、地元の大学生団体「ベジガール」との商品開発プロジェクトへの参画、役員会での給与検討会議への参加など、日常業務の中にある価値を学生に体験してもらいます。
また就労支援事業「明り」での活動を通じて関係性を築いた学生もおり、別の内定を辞退してまで入社し、現在は新店舗の店長として活躍している事例もあります。
愛媛経営研究会での実践〜トライアル入会の成果
橘代表は自社の取り組みを愛媛経営研究会でも実践されました。
同会は例会出席率が47%まで低下し、84ヶ月連続入会を続けた結果、会費未納者が増加するなど質の問題も抱えていました。
そこで「トライアル入会」を導入。
「内定辞退率は採用に関わる人数に反比例する」というデータを活用し、会長・事務局長だけでなく、理事や一般会員も含めて多くの人がトライアル生と関わる仕組みを構築しました。
5期にわたる取り組みの結果、68名が参加し44名が入会(入会率約65%)。例会出席率は47%(最低時)から82-83%(現在、85%達成予定)まで向上し、会員数も130名→100名切る→110-120名まで回復しました。
特筆すべきは本部研修参加率の向上で、去年入会した2名が今年TTに参加し、両名とも社長を務めるなど、質の高い会員が増加しています。
橘代表は強調します。
「入会した人がどれだけ満足したかが重要な指標。入って良かったと胸を張って言えるかどうか。この体験がないと、次の人に勧めることはできない」
開催概要
• 日時:2025年7月23日(水)18:00-20:30
• 会場:TIME SHARING 銀座三丁目ビルディング5階
• 主催:東京経営研究会 ありがとう経営推進委員会
今回の講演で最も印象的だったのは、「共感」が単なる精神論ではなく、具体的な業績向上に直結する経営戦略であることでした。技術革新が進む現代においても、最終的に企業の成功を左右するのは「人」であり、その人と人とのつながりを深める共感の力が不可欠であることを、実体験を通じて学ばせていただきました。橘代表、藤田取締役には、貴重な体験談と実践的な知見をお話しいただき、誠にありがとうございました。