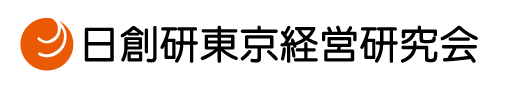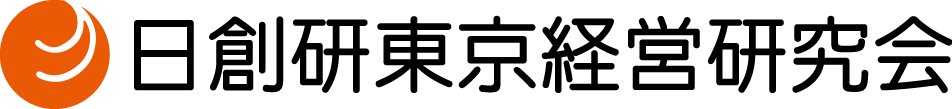2025年8月18日、東京経営研究会8月例会にて、株式会社冒険王の堀岡宏至代表取締役にご講演いただきました。
2025年8月18日、東京経営研究会8月例会にて、株式会社冒険王の堀岡宏至代表取締役にご講演いただきました。
「今こそ、冒険しよう!~冒険王が示すシン・リーダーシップ~」というテーマのもと、先代から受け継いだ玩具小売業を売上80億円まで成長させた実体験を通じて、現代のリーダーシップのあり方について貴重なお話を伺いました。
創業の精神を受け継ぐ三代目経営者
堀岡代表は42歳、7歳と5歳の男の子を持つ父親でもあります。
先代である父・堀岡洋行会長の三男として生まれ、大学卒業後は全く異なる業種である電子カルテシステム開発会社に16年間勤務。
38歳まで「おもちゃを知らない」状態でしたが、2021年に冒険王に入社し、翌年6月に社長就任という異例の経歴を持つ経営者です。
講演冒頭では、田舞徳太郎代表に制作いただいた創業の精神を描いた動画が上映されました。
祖母シズの「儲けることは強い相手とは決して戦わないこと。
アイデアのない商売は広がりがない」という言葉から始まる物語は、外資系大型玩具店の進出で売上が4割減少した危機を、固定観念を打ち破り「大人向けホビー」に特化することで乗り越えた軌跡を描いています。
現在、北は岩手から南は鹿児島まで65店舗を展開し、前期は過去最高の業績を達成されています。
日創研との出会いと急速な成長
 堀岡代表の日創研との出会いは劇的でした。
堀岡代表の日創研との出会いは劇的でした。
2021年12月、前職の退職3ヶ月前に父と共に日創研を訪問した際、田舞代表から「来月から来い」と言われ、起業家養成スクールを受講。コロナ禍でほぼオンライン研修という厳しい条件下でしたが、翌年6月には社長就任という異例のスピード昇進を果たしました。
現在も社長塾、マネジメント養成コース、業績アップ上級コースなど継続受講中で、「新しい時代の社長学」も今月から受講予定です。
同社の教育システムは段階的で体系的です。
アルバイトから正社員への登用を基本とし、アンバサダー養成(新設)→店長塾→マネジメントレビューという流れでOJTとOFF-JTを組み合わせた育成環境を構築。
特に注目すべきは、業績アップ6ヶ月セミナーに常時1名以上を派遣し、SGAも入社2年以内の全員受講とコアメンバー昇格条件にしている点です。
共感をベースとしたリーダーシップ論
堀岡代表のリーダーシップの核心は「共感」です。
「リーダーシップは共感。どれだけ従業員や共に働く仲間に共感してもらえるかが全て」と断言されています。共感を得るべき対象として、①共に働く仲間(従業員)、②真の顧客(子育て世代のお父さん)、③取引先(問屋・メーカー)を明確に定義し、全ての経営資源をこの3者から共感を得るために機能させることを徹底されています。
同社の企業文化の特徴は、商品好き→仲間好き→お店好き→お客様好き→仕事好き→会社好き→もっと勉強→また商品好きという好循環サイクルです。
これを支えているのが先代から続く「現場主義」で、役員全員が店長経験者という徹底ぶり。
経営資源の優先順位「人・情報・物・金」は堀岡代表の7歳の息子も言えるほど企業文化に浸透しており、この順序を守る経営を実践されています。
スクラップ&ビルドによる生産性革命
同社の成長戦略で注目すべきは、店舗数を増やさずに売上を向上させる「スクラップ&ビルド」手法です。最盛期72店舗から65店舗に減らしながら、売上は大幅に向上させています。
イオンモール広島府中店の事例では、3店舗(呉・アルパーク・西条店)を集約し、売り場面積120坪→92坪、従業員9名→5名にしながら、1人当たり売上を大幅に向上させ、高い営業利益率を実現しました。
同様にイオンモール徳島店では、売り場面積49坪→100坪に拡大、運営人数は変えずに1人当たり売上を大幅に向上させています。
前期は全体で307坪の売り場拡大、5名の人員削減で大幅な売上増を実現。
この手法により「1人当たりの売上を上げるために、1人当たりの売り場面積を広げる」戦略を確立し、生産性向上と働きやすさの両立を図っています。
エンパワーメント経営の実践
堀岡代表は社長就任後、ケン・ブランチャードの「エンパワーメント」理論を経営に導入しました。
「社員は会社のために尽くそうとしているのを堰き止めているのは経営者」という前提のもと、3つの鍵を実践しています。
第1の鍵「正確な情報を全社員と共有」では、グロースカレッジの導入、役員会議の廃止、全社ミーティングの開催で情報をフラットに共有。
星野リゾートを参考に「さん付け」を徹底し、役職呼びを廃止して偉い人信号をなくしています。
第2の鍵「境界線を明確にして自律的な働き方を促す」では、創業の精神動画の制作、理念学習の毎月実施、段階的教育体系の構築を実行。
第3の鍵「階層組織をセルフマネジメントチームで置き換える」では、縦の組織(4つのエリア)と横の組織(5つのプロジェクト)を組み合わせ、自律的な活動環境を創造しています。特に降格人事も積極的に行い「降格がない組織ほど緊張感がない」として組織の活性化を図っています。
主力商品の戦略的再定義
 社長就任2期目の大きな取り組みが「主力商品の再定義」でした。
社長就任2期目の大きな取り組みが「主力商品の再定義」でした。
従来の5本柱(プラモデル、フィギュア、トレーディングカード、食玩、ジグソーパズル)から、現場が本当に売りたいものに絞り込んだ「3本の矢」に変更しました。
①満足の矢(ジグソーパズル):売り場の顔となる商品、
②創客の矢(ミニチュア):ガチャガチャの箱版やトミカなど、お客様を作る商品、
③演出の矢(ガンダムプラモデル、ポケモンカードなど):お客様の熱狂を作る商品という分類です。
この再定義により、現場との方針ギャップが解消されました。
印象的なエピソードとして、店舗移転時に他店への移動を勧めたアルバイトスタッフが「社長の主力商品に僕の好きなものがない」と言って辞めた件を紹介。
「現場が生き生きとプライドを持って働くためには、現場とのミスマッチをなくすことが重要」と強調されています。実際に構成比は大きく変化し、粗利の高いミニチュアが51%まで上昇、販売総利益率も大幅に向上しています。
組織改編の継続的実践と「降格人事」の積極活用
堀岡代表は就任以来、継続的な組織改編を実践しています。
縦の組織では、当初11の小集団活動から8つのエリア、そして現在の4つのエリアへと段階的に統廃合。
特に東日本と西日本の「変な派閥争い」を解消するため、ブロック制を廃止し統一組織に変更しました。
横の組織では、20数個あった委員会活動を7つのプロジェクト活動に集約し、さらに5つに統廃合。全員参加制から選抜制に変更し、プロジェクトリーダーの任期を2年として定期的に交代させています。
特に注目すべきは「降格人事」への積極的な取り組みです。
堀岡代表は「降格がない組織ほど緊張感がない組織はない」と断言し、成果を出せないリーダーは積極的に降格させています。
「降格理由もしっかりと伝えた上で、社長自ら言うべき」として、組織の活性化を最優先に考えた人事を実践。役員組織も大幅に見直し、フラット型からピラミッド型に変更し、濱岡氏を副社長に昇格させる一方で、29歳の楠本氏、森脇氏を新たに執行役員に登用しました。
これらの大胆な組織改編により、65店舗という多店舗展開における情報共有とコミュニケーション改善を実現しています。
データ分析に基づく戦略立案
同社の強みの一つが、豊富な販売データを活用した戦略立案です。
日本玩具協会発表によると、2024年度の国内玩具市場は前年同期比107.9%の1兆992億円と初の1兆円突破を記録。
少子化が進む中での市場拡大は、同社がターゲットとする「大人向けホビー」戦略の正しさを証明しています。
堀岡代表は「子供向けのお店には大人は行けない。大人っぽいお店に大人が行って、その結果として子供も一緒に来る」と分析。
実際、業界平均の1.5倍の商品回転率を実現し、イオンモールからも「男性客が行ける店が少ない中でのニッチな需要」として重宝されています。
さらに注目すべきは、年間14万人の有料会員獲得と、間もなく100万人に達するアプリ会員数。
この顧客データを活用した新ビジネスモデル「情報分析業」「開発コンサル業」の構想も発表され、「本業を強めるためのイノベーション」として位置づけています。
人材育成における「モデリング」の重視
堀岡代表が最も重視するのが「モデリング」です。前職で16年間、優秀な上司に恵まれた経験から「上司に恵まれない部下ほどかわいそうなものはない」と痛感。4名のエリアマネージャーを「モデルとなる人材」として厳選し、憧れのステータス作りを徹底しています。
副社長の濱岡氏について「ものすごい勉強熱心で、玩具業界のことを手取り足取り教えてくれる大番頭的存在。
年齢は同じ42歳だが、先代を尊敬し、自分を支えてくれる本当に良いクリエイティブペア」と紹介。
「クリエイティブペアが頑張ってくれるので、自分ももっと勉強しなければいけない。
ボスマネジメントされているような感覚」と述べ、相互成長の関係性を築いています。
教育面では、SGAを「コアメンバーへの昇格条件」とし、受講者にはエリアマネージャーや役員を必ずサクセスパートナー面談に参加させるなど、社長自らが関わることで効果性を高めています。
次世代ビジネスモデルへの挑戦
同社は現在の成 功に満足することなく、次世代ビジネスモデルの構築に取り組んでいます。
功に満足することなく、次世代ビジネスモデルの構築に取り組んでいます。
現状のターゲット「子育て世代のお父さん」から、将来は「アジア人ファミリー観光客」への展開を構想。東京23区、駅、空港ターミナルなど「帰りに寄れる場所」への出店で、日本土産としてのホビー商品販売を目指しています。
また、65店舗の販売データを活用した「情報分析業」では、特に地方の販売情報をメーカーや問屋に提供するサブスクリプションモデルを検討中。
「地方の情報は都市部と違って収集が困難で、メーカーも欲しがっている」として、月額制での情報提供ビジネスを構築予定です。
さらに「開発コンサル業」では、販売力という強みを活かし「共に売る」という関係性でメーカーの商品開発に参画し、人材派遣も行う構想を発表。
これらの新規事業で得た利益を出店や人材育成に再投資する好循環を目指しています。来期予算も大幅な増収を見込んでいます。
先代から受け継いだ「人・情報・物・金」の優先順序を徹底し、継続的な組織改編と人材育成により、急速な成長を実現されています。
特に「社員は会社のために尽くそうとしているのを堰き止めているのは経営者」という認識のもと、エンパワーメント経営を実践し、自律的な組織運営を目指す姿勢は、多くの経営者にとって参考となる内容でした。
参加者からは「誠実さが伝わった」「やる気が高まる講義」「ヒント満載」といった評価をいただき、「学びを実践し続けること」「降格人事の導入」「現場主義の徹底」など、具体的な実践意欲も多数寄せられました。
堀岡代表には、貴重な実体験と具体的な手法をお話しいただき、誠にありがとうございました。
参加者一同、大きな学びと刺激を得ることができました。