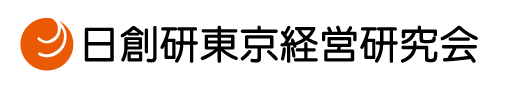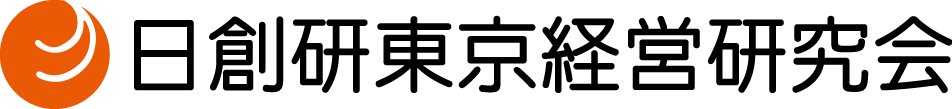9月例会は経営研究会の一丁目一番地ともいうべき「経営プレ発表大会」でした。
9月例会は経営研究会の一丁目一番地ともいうべき「経営プレ発表大会」でした。
これは毎年全国の会員が集まって各企業の経営方針を発表するという「全国経営発表大会」に向けた、単会で行うリハーサルとも言える大会です。
他では経験し得ない独自の取り組み

決まったフォーマットに会社情報、業界情報の整理と経営環境に対する分析を行い、財務まで含めた中長期から短期の経営方針計画書としてまとめ、同じ立場の会員に発表するというものです。
経営研究会の最大の行事であり、他では真似のできない取り組みです。
ではなぜ、経営研究会では財務まで含めた経営計画を第三者に発表することができるのでしょうか。
それは、経営研究会の会員が日創研の可能思考研修を修了することで「共に勝つ」という共通の価値観を共有し、学びの土台にしているからです。
発表者も、その発表を聞いてフィードバックする側も「自分のため」ではなく、お互いもしくはそれぞれが「関わる人のため」にこの場を通して学ぼうとする姿勢を持ち合わせ、「共に勝つ」という価値観をここで体現、実践しようとするからです。

もし、会員がこの土台となる価値観を持ち合わせないまま経営発表をしたらどうなるでしょうか。
お互い自分のためだけに発表、フィードバックすることになり、恐らくその場は互いの主張をぶつけ合うだけの修羅場になることでしょう。
そもそも疑心暗鬼が高じて情報を共有することすらできないかもしれません。
日創研経営研究会の経営発表大会はそれほど特別なものであり、経営者が最も学び成長できる機会なのです。
相手に共感され影響を与える「伝え方」を学ぶ

また、経営発表が実践的であると言えるのが、「誰に対して発表するものか」を最初に明確にすることです。
同じような経営者の集まりでも他の経営者に何かしらの発表をすることはありますが、大抵の場合それは同じ立場の他の経営者に自分の考えなどを述べるだけです。
その場合重視しているのは、単に自分の意見を他人に「発表する」ことだけであり、言いたいことをまとめたり人前で話す度胸はつくかもしれません。
しかし、経営者や組織のリーダーに求められるのはそれだけではなく、むしろ相手に自分の思いや考えを「伝える力」と、相手に行動を起こさせる「動機づけ」です。
これは机上の理屈だけで学べるものではなく、体験や訓練によって得られる能力です。
 いくら良いことを言っているつもりでも、相手に伝わり、相手の心に響かなければ相手は動くことはなく、結果的に何の変化も成長もありません。
いくら良いことを言っているつもりでも、相手に伝わり、相手の心に響かなければ相手は動くことはなく、結果的に何の変化も成長もありません。
本気の取り組みが新しい気づきを生む
 今回7名の方が登壇し、それぞれの経営方針を発表してくれました。
今回7名の方が登壇し、それぞれの経営方針を発表してくれました。
今回初めて発表される方から、毎年のようにこの場で経営発表している方まで様々でしたが、発表を終えた方が口を揃えて言うのは「発表とフィードバックから新しい発見があり楽しかった」ということです。
中には代表を引き継いだ現社長の発表に対して、前社長であるオーナーが任せ・任されたことに対する思いを伝え合うことで、互いの至らなさと思いを確認し合い、感情があふれ出るという感動的な場面もありました。
この経営発表の場がなければ、互いの思いはいつまでも平行線を辿っていたかもしれません。
形式的な発表ではなく、本気で経営に取り組み、相手に伝えるための発表をしたからこそ生まれた新しい発見、気づきでした。

もし、経営に停滞感やどこか社内の意思疎通に課題を感じる、あるいは自社分析や経営環境に不安を感じると言う会員の方は、課題突破のきっかけにこの経営発表に取り組んでみてください。