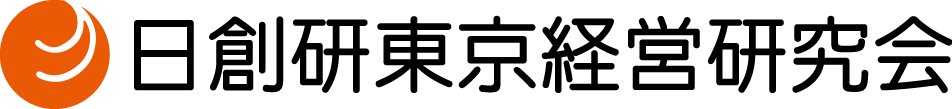なぜ会社からのメッセージが届かないのか?
集客や採用活動でメッセージを送っても反応がない、多くの企業、とりわけ中小企業の活動で起こっており、リソースに乏しい中小企業にとって大きな課題になっています。
原因は様々考えられますが、大きく2つに分けられます。
一つはチラシやポスターあるいはSNSなどネット上のツールが活かされていないという「物理的」な要因。もう一つは相手が反応してくれない、つまり心に響いていないという「心理的」な要因です。
ただ、物理的な要因であっても心理的な要因が根本であることがほとんどで、「頑張って取り組んでいるのに成果が出ない」のは心理的な要因が解消されていないからなのです。
その理由は、「伝える」と「伝わる」の違いにあります。
「伝える」ために必要なのは対面での営業活動やメールや電話といった「手段」です。一方「伝わる」ために必要なのは伝える「相手(の興味・関心)」です。
「伝わる」とは状態を表しますが、心理学的にいうと以下のように説明されます。
「相手がメッセージを“積極的に”理解し、共感すること」
メッセージを理解しただけでなく、共感しないと伝わったことにならないというのは、理解と共感の違いを見ればわかります。
 理解とは「わかる、相手が言う理論・理屈を相手と同じように受け入れた状態」ですが、共感は「納得する、相手の言いたいこと、相手の心情までを受容し噛み締められた状態」であり、心理学的には「自分にもできそう」という自己効力感から親近感を抱かせ心情を共有すること、だとしています。これは、「共感」によって行動が喚起されやすいということが言えるのです。
理解とは「わかる、相手が言う理論・理屈を相手と同じように受け入れた状態」ですが、共感は「納得する、相手の言いたいこと、相手の心情までを受容し噛み締められた状態」であり、心理学的には「自分にもできそう」という自己効力感から親近感を抱かせ心情を共有すること、だとしています。これは、「共感」によって行動が喚起されやすいということが言えるのです。
つまり、集客や採用活動で人が集まらない、メッセージを送っても反応が無い理由は、そのメッセージが共感されていないということが言えます。
共感のメカニズムとバイアス
ではなぜ、集客や採用活動における多くのメッセージが共感されないのでしょうか。
共感の心理学的解釈には「相手の感情を読み取りそれに寄り添うこと」だとされていることから、メッセージが共感されないのは「相手の感情を読み取れていない」からだと言えます。
実はこの感情を読み取る力というのは人間だけが持つ能力であり、現時点ではAIが可能なのは顔の違いを識別することだけで、顔の表情から感情を読み取ることまではできません。
感情は話す言葉だけでなく、表情や様子など様々な背景を含めた「全体」からしか読み取れません。感情を読み取れないAIには相手に共感することは難しいのです。
共感は人にしかできない能力であるのにメッセージが共感されないのはなぜでしょうか?
実は私たちは共感が生まれない、共感することを阻むようなことを無意識のうちに行なっています。それが「確証バイアス」です。
確証バイアスとは、同じ環境にいることで、そこでの経験(成功・失敗)や体験したことが脳に長期記憶として蓄積され、判断の際の直感として優先されることで現れる、言わば脳の省エネ機能の一つ。
 例えば、満員電車の中で高齢者に席を譲るという行為は本来誰もが行うべきものですが、譲らなかったり寝たふりをするなど人によって行動パターンが異なるのはこの確証バイアスが働いているからです。つまり、過去に同じような状況において声をかけたが断られたり、逆ギレされたといった嫌な気持ち、感情を繰り返し味わったこと(他人の行為を見たことも含め)があると、それが長期記憶となり高齢者に対する「これが正しい」という考えが脳内で形成され、高齢者を見ると無意識のうちに自分の中でその行動をしてしまうのです。
例えば、満員電車の中で高齢者に席を譲るという行為は本来誰もが行うべきものですが、譲らなかったり寝たふりをするなど人によって行動パターンが異なるのはこの確証バイアスが働いているからです。つまり、過去に同じような状況において声をかけたが断られたり、逆ギレされたといった嫌な気持ち、感情を繰り返し味わったこと(他人の行為を見たことも含め)があると、それが長期記憶となり高齢者に対する「これが正しい」という考えが脳内で形成され、高齢者を見ると無意識のうちに自分の中でその行動をしてしまうのです。
KKDH経営に気づく
つまり、確証バイアスがあると相手に対する「思い込み」や「決めつけ」といったいわゆる「色眼鏡」で見てしまい、表情や様子など背景を含めた全体が見えなくなることから、相手の感情を読み取ることができなくなるのです。
この確証バイアスは誰もが持っているものであり、それが悪いということではありません。経験からくる勘も同じような脳内の省エネ機能であり、これがなければ現代のような情報に溢れた社会では処理しきれず倒れてしまいます。
大切なのは、相手の感情を読み取らなければならない場面において、自分の中にある確証バイアスに気づいて、それを働かすことなく相手の感情を読み取るということです。
確証バイアスによる「思い込み」や「こだわり」は仕事上におけるメッセージが伝わらない、共感されない理由の一つですが、その影響力は小さくありません。
特に仕事上で形成される「思い込み」や「こだわり」とは、過去の成功や失敗の体験からくるものです。
「これまでこのやり方で上手くいっていた」「我が社の顧客とはこういう人」というのは、その多くが根拠のない主観でしかありません。つまりKKDH(勘、経験、度胸、ハッタリ)経営と言われる基こそが「思い込み」や「こだわり」という確証バイアスなのです。
これに気づいて取り除いた上で相手にメッセージを届けなければ、いつまでたっても共感されず結果伝わらない、何の成果も得られないということになるのです。
共感されるメッセージを作る準備
では、共感され伝わるメッセージを作るにはどうすれば良いのでしょうか?
先ほど、仕事上の「思い込み」や「こだわり」はその多くが根拠のない主観、だと言いましたが、共感され伝わるメッセージを作るためにはこれとは逆に「客観的な根拠を集めて分析する」、ことが必要になります。
つまり、それぞれの企業の商品・サービスや事業が顧客に求められたのか、顧客はどのような理由から購買に至ったのかを、売上に関する様々な数値や取引が成立するまでの具体的なプロセスから読み取るということです。
共感を生むために必要なのは相手の感情、ここでは顧客や顧客となるユーザーの感情を読み取る必要があります。そして、その感情を読み取るためには売り手に存在する思い込みやこだわりといった確証バイアスを除いた客観的な事実のみを根拠としなければいけません。
そのためのリサーチや分析が無いままにメッセージを伝えることばかりしても共感されることはなく、望むような結果や成果は得られません。
分析手法は様々ありますが、大事なのはとにかく具体的で正確な数字を基にすることです。
3C分析やPEST分析、SWOT分析などが有名ですが、いずれも具体的な数字を基にしないとどうしても思い込みやこだわりといった主観による言わば「希望的観測」によったものになってしまうので注意が必要です。
その上で顧客やユーザーの感情を読み取る上で欠かせない3C分析について、その具体的な分析方法を解説していきます。
顧客の現状を細分化する
 3C分析の3Cとは顧客(Customer)、競合(Competitor)、自社(Company)のことで、マーケットに存在する3つのプレーヤーの特徴、関わりや比較を通して共感の素になる「ニーズ」を浮き彫りにするための分析です。
3C分析の3Cとは顧客(Customer)、競合(Competitor)、自社(Company)のことで、マーケットに存在する3つのプレーヤーの特徴、関わりや比較を通して共感の素になる「ニーズ」を浮き彫りにするための分析です。
まず顧客(Customer)ですが、ここでの分析の目的は売上(事実)と販売特性(売れている背景)から相関関係を分析する「顧客の見える化」です。
そのためにまず自社の強み、すなわち売れ続けている要因を因数分解して、分析する数字について確認をします。
強み=売れ続けている理由
=売れ続けている商品の特徴 × 買ってしまう理由
=(販売実績+機能的価値) ×(情緒的価値+差別化)
=(売上+販売特性+機能的価値)×(ベネフィット+コンセプト+差別化)
この中で具体的数字を基に分析するのが販売実績を表すの2つの項です。
販売実績は売上と販売特性に分解でき、売上とは商品ごとの売り上げデータ(単価 × 数量)、販売特性とは繁閑特性、顧客特性、流入元のことです。
販売特性とは商品・サービスの販売時の特徴であり、売れる背景を示す数字のことです。繁閑特性とは売れる時間帯や時期など時間軸で売り上げの変化を見るもの。顧客特性は性別や年齢、職業職種、業界、新規・再販など顧客の特徴で分類し分布を見ます。そして流入元は購買の起源となったものを分類し分布を見ます。
つまり、売り上げデータからは商品・サービスごとの売れる傾向(欲しいモノ、価格バランス)が読み取れ、販売特性からは顧客層(カテゴリー、背景)が読み取れます。さらに、2つを組み合わせて分析をすることで、顧客像のアウトラインがより明確に浮かび上がります。
3つのベンチマークを持つ
次に競合(Competitor)ですが、ここでの分析の目的はベンチマークを設定し自社の機能的価値の優劣とニーズの強弱を分析する「ニーズの見える化」です。
ベンチマークとは、優良他社とその戦略を指標とし、その比較から状況を改善する活動のことで、その対象は自社と事業内容や規模が近い同業他社に限らず、異なる事業領域(競業)や異なる業界(異業種)において優れた結果を出している企業(海外も含めて)になります。
ここで気をつけるべきは、競合を単なるライバル会社(同業)だと考えるのではなく、同業も含めた自社の商品・サービスおよび事業に関連する企業を自社の比較対象にするということ。同業をライバルというのは言わば自社目線であり、顧客やユーザーにとってはそこに関心はありません。顧客やユーザーの関心事は自分の中の問題や悩みの解決であり、その意味では競業や異業種であっても良いわけです。
分析すべきは顧客やユーザーが何を求めているのか、顧客やユーザーにとっての価値は何であるか、ということです。
3つのベンチマークを設定し、自社との比較をしていくのが競合(Competitor)における分析です。
①同業:同じ市場のいわゆる競合ですから、機能的価値の比較を行います。同じ商品・サービスにおける価格や性能・機能の数値による比較をします。
②競業:ニーズは同じだがソリューションが異なるものですから、ソリューションの比較を行います。例えば外食に対する中食(なかしょく)などですが、選択される理由や背景を様々なデータから読み取り、ニーズの強さ(選択させる影響力の強さ)を測ります。
③異業:全く別の業界だが、目標にできる優れた企業であり、情緒的価値の比較・分析をします。情緒的価値とは具体的解決策(ソリューション)によってユーザーが受け取る感情的な価値のことで、商品・サービスのベネフィットやコンセプトのこと。異業は全く異なるニーズに応える企業なので、そのニーズが求められる理由やその強さとマークする企業の情緒的価値を分析します。
自社の現在地を俯瞰する
最後に自社(Company)です。
自社の事業あるいは商品・サービスの分析をするのですが、顧客(Customer)分析において売れている商品・サービスの分析をしていますから、ここでは自社が現在置かれているマーケットの状況を「ポジショニングマップ」を使って分析します。
ポジショニングとは、競合と比較した時の自社製品の差別化あるいは訴求ポイントを分析するためのもので、様々なニーズを縦軸×横軸に設定、市場や競合との位置関係を明らかにし、ユーザーへのアプローチを戦術的、戦略的に考える基にするものです。
マーケットにおける購買決定要因、つまりユーザーが商品・サービスを購入する上で重視する価格を含めた機能的要素からポジショニングマップを作成していきます。
まずは購買決定要因を分析、そのうちの2つを縦軸と横軸にして、自社および競合他社の位置関係を見ます。
大抵の場合、競合他社(同業)との比較するためにこのポジショニングマップを使用しますが、ニーズの多様化や価値観の変化、あるいは人口動態によってこれまでのユーザーが必ずしもユーザーであり続けるとは限らないので、あらゆる角度からマーケットを見ていくことが大切です。
実際にこれまである特定ユーザー向けに作っていた商品が、使用目的は同じでもまったく異なるユーザーがこれまでとは異なる場所で商品を使用し、大きな注目を集めることになったという例がたくさんあります。
企業がユーザーを追いかけている
老若男女にスマートフォンが行き渡り、コミュニケーションの中心がSNSになったことで、マーケットの中心は確実にユーザーとなってきています。
これまでは、マーケットのリーダー企業によるニーズ分析から生まれた商品・サービスがマーケットに投下され、それに追随する企業が少しずつの差別化によってユーザーを獲得しようとするという構図でした。
これはマーケットの情報、つまりニーズはもちろんのこと、商品・サービスの情報や競合他社の情報を集めることが困難であり、リーダー企業(大手企業)による費用をかけた分析や商品・サービスづくりに委ねるしかなかったからです。
同時にユーザーも情報を得るための手段が4大媒体(テレビ、ラジオ、新聞、雑誌)に限られていたため、企業から提供されるものを提案通りに使うしかありませんでした。
インターネット、さらにスマートフォンが普及し、SNSによるコミュニケーションが電話やメールよりも使われるようになった近年、これまでの構図が大きく変わりました。
ここで注目すべきは、この変化が企業によって「意図された」ものではないということ。それぞれの技術の進歩が我々の潜在ニーズを呼び起こし、私たち自らがこれまでの生活スタイルやコミュニケーションを変えていったという点です。
確かにその技術を提供し、ツールとして使い方や方法を提案した企業が存在しますが、コミュニケーションの質や価値観を変えたのはユーザーだということ。いつしか企業はユーザーの変化や価値観を追いかける、という構図に変わっていたということです。
価値観の変化を捉えて変化する
これは言わば「スマホ総メディア化」です。
これまでの4媒体によって独占されていた情報は、費用を出して得る、もしくは必要のない情報までも見せられてきました。それが現在では、ほとんどの人がスマートフォンによってネットから「見たい情報だけを無料で得る」ことができるようになりました。
これが意味するのは、これまでのような企業側から発信される一方的な情報の価値が下がったと言えます。相対的に価値が高まっているのが「共感できる情報」です。
「共感できる情報」とは冒頭に共感について説明した通り、「相手の感情(やりたい、なりたい)を考えた情報」のことで、ズバリ「家族や友だちからの情報」のことです。SNSのコミュニケーションがここまで広がったのはこのためです。
では、企業やこれまでのメディアからの情報は全く見向きされなくなったかというと、そうではありません。このユーザーの「価値観の変化」を捉えることができた企業やメディアはこの「共感されるメッセージ」を発信するために自らを変えて、ユーザーとコミュニケーションを図っていますし、ユーザーもネットとスマートフォンで情報を取りつつ発信をしています。
つまり、この項の冒頭で述べた通り、マーケットの中心は中心はユーザーになり、ユーザーが共感による取捨選択をしているのが今のマーケットなのです。
さらに注目すべきは、ユーザー自らが情報の発信源にもなり、インフルエンサーとして多くのフォロワーを抱えた個人は、その影響力から個人でありながらもはや巨大なメディアとなっているのです。
共感を生むためのリサーチを
これらマーケットの変化に対応していくにはどうすれば良いのでしょうか。これからの「スマホ総メディア化」時代に対応し生き残るために中小企業がやるべきは2つです。
①顧客だけでなく、自社に関わる人(スタッフ)や企業(パートナー)に共感されるメッセージを生み出すこと
②外部業者への代行依頼など人任せにせず、自社内でマーケットのユーザーとのコミュニケーションを図る
情報発信などを外部業者へ代行依頼することがいけないわけではありません。ただ、依頼するためにもまず会社がユーザーとのコミュニケーションを自律的に行えるようになる必要があります。代理店や代行会社はあくまで「作業の代行」をするだけですから、①ができるのは「思いを持った」自社にしかできないことだからです。
そして、ユーザーとのコミュニケーションを成功させる最大の鍵は「リサーチ」にあるということです。
これからはユーザーに共感されないといけないわけですから、とにかくユーザーのこと、ニーズやベネフィットを知らなければいけません。そのためには自らの思い込み「バイアス」を捨てて、客観的に自社を含めたマーケットを見ていく必要があります。
客観的なデータを元にユーザーとの接点、共感されるものを見つけ出し、さらにユーザーの「意識レベル」に応じたメッセージを考えていく。
つまり、情報を発信することばかりを考えるのではなく、発信すべき情報の調査・分析のための「リサーチ」の差がこれからのマーケットにおいて大きな意味を持つのです。