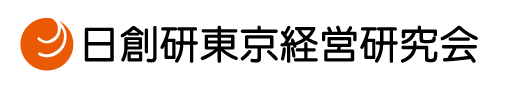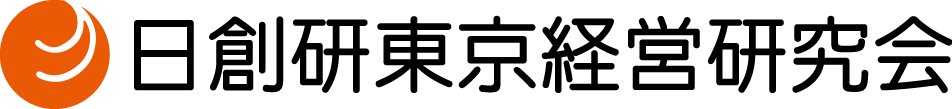今回は静岡県浜松市で400年前から13代続く農園を営み、現在「ユニバーサル農業」で注目されている京丸園株式会社の鈴木厚志社長に講演していただきました。
遭難していることに気づいた30歳
 長男だった鈴木講師は、20歳で京丸園を継ぐ形で家に入りました。
長男だった鈴木講師は、20歳で京丸園を継ぐ形で家に入りました。
当時はまだ家族経営だった京丸園でしたが、農業高校、農業大学を卒業した鈴木講師は、農家の長男という同じ境遇の人たちが集まるような学校だったこともあり、同級生には負けたくないと10年間がむしゃらに仕事しました。
10年働いて成功者の証としてベンツに乗って同窓会に行く、そんなことを考えて一生懸命働きました。
朝5時から夜中の12時まで働いて、20代の鈴木講師はその後遊びに行って、少し寝てまた仕事する、そんな10年間を過ごしました。
10年間人の倍以上働けばベンツを買っても良いだろう、だから30歳の時に買ったベンツが駐車場にある。
30歳の誕生日のプレゼントで妻が持ってきてくれたケーキにろうそくをさして火をつけた。
火をつけた時にはあった駐車場のベンツ、吹き消したら車庫の中にあったのは10年前と同じ車。
マッチ売りの少女のように、マッチをすった時にはあった夢のような世界が消えると現実の世界が待っていた、鈴木講師は当時の心境をそのように語りました。
働かず遊んでばかりいたからベンツが買えなかったのなら納得できるが、人の倍真面目に一生懸命働いのに車1台変えられなかった。
ベンツとは言わないとしても、車も変えられなかったわけですから、鈴木講師は現実が受け入れられませんでした。
親や先輩たちからは「真面目に働けば夢は叶う」とか「念じれば花開く」といったことをいろいろ言われたから、鈴木講師は一生懸命働いたのに何も変わらなかったことで、一気にやる気を失くしてしまいました。
そんなある時、行政による「農業経営戦略講座」という勉強会が開催され鈴木講師も参加しました。
その中で講師の先生から、三つ質問に対する回答を具体的に書くように言われました。
「なぜ農業やってんのか?」
「どんな農園にしたいの?」
「どんな仲間とこれから一緒に経営をやっていくつもりなの?」
失意の中にあるとは言え、20歳から10年間一生懸命働いてきた当時30歳の鈴木講師でしたが、この三つの質問に一つも答えられませんでした。
三つの質問に答えられなかった鈴木講師に対してその時の先生が言ったのは、「もし、今この三つの質問を答えられないとしたら、それは経営してないよ」。
経営というのは逆算であり、ゴールが決まっていないというのは経営していることにならない。
質問答えられないということは、ゴールが決まっていないからだと。
そして先生は言いました「そういう人たちのことを経営者ではなく遭難者というんだ」。
船船で太平洋に地図も持たずに出向したら、それは遭難している、道に迷っている人だと言われ、その時初めて鈴木講師はそれが今の自分であることに気づきました。
朝から晩まで農作業はやってたけど、経営をしていなかった、ゴールが全然決まっていなかった。
当時30歳の鈴木講師にとって、それが経営の勉強のスタートになりました。
理念や戦略、戦術を常に考え続けるのが経営者であり、なぜ農業やっているのか、どんな農園にしていきたいのか、そしてどんな仲間と歩んでいくのかという具体的な答えを常に自分に問いかけていく、そういうことを考え始めた時のが30歳でした。
働くことの意味に気づいた30歳
 実は鈴木講師にとって30歳は大きな転換点であり、いろいろなことが起きました。
実は鈴木講師にとって30歳は大きな転換点であり、いろいろなことが起きました。
経営の勉強を始めたことが一番大きことでしたが、障がいを持った人たちに出会ったのもちょうど30歳の時でした。
農業は面積を拡大したり、生産量を増やそうとしたら、それだけの人を入れないと回りません。
そこでパートさんを集めるために求人を出し、いろいろな人たちが集まってきますが希望する人はなかなか来ません。
面接に来るのは決まって高齢者か障がいを持った人たちの親子しか来てくれません。
そんなある日、京丸園さんに求人の件だという電話がありました。
応募の電話かと思いきや、言われたのは「オタクの求人だけど、最低賃金割れてますよ」。
鈴木講師は「その時初めて世の中に最低賃金というのがあることを知った」と言い、「正直なところ、結局最低賃金に満たないような金額しか出せなかった」ということでした。
しかし鈴木講師は、京丸園さんが世間の相場とずれていたということ以上に、それにも反応してくる人もいたということに気になったと言います。
高齢者の近所のおじいちゃん、おばあちゃんとかや障がいを持った人たちが、その条件でも来たということがある意味で一つの発見でした。
障がいを持った人たちは一人ではなく、大半が母親と一緒にきて「息子なんですけど」という形で面接に来ます。
でも当時の鈴木講師は、障がいを持った人たちは働けないと思っていたため、来たとしても断ることを決めていたと言います。
履歴書を出されても、無理だと思いますと言って封も開けないでつき返します。
すると母親は「そんなこと言わないで、私も一緒にサポートつきますから、なんとかうちの息子を雇ってほしい」と言ってきます。
しかし、障がいを持った人たちが母親と一緒にきて一緒に働くというのは自分の考える働く姿ではない、それは無理だと言って再び返します。
すると母親はもう一度履歴書を鈴木講師に出して、「お給料いりませんから働かせてください」と言ってきました。
それを聞いた鈴木講師は驚くと同時にその母親を訝しんだと言います。
なぜなら、当時30歳の鈴木講師の中では、お金稼ぐために働くのだ、働く理由はお金のため以外にはなかったからです。
それが常識だと考えている人間からすれば、「お金いらないから働かせてくれ」という母親の言葉は疑問でしかなく、「申し訳ないけどお母さんもちょっと変わったこと言う人かな?」と受け取り、一二歩後退りするような姿勢で、無理とだけ答えて帰ってもらったということです。
しかし、親子を帰らせて後も鈴木講師は「なんであんなこと言うのだろう」と母親の言葉が気になりました。
そこで、鈴木講師は福祉事業所に勤めている友達がいたことから、給料要らないと変わったこと言う親子がやってきたという話をし、どういう意味なのかわかるか聞いてみました。
するとその福祉に携わっている友達は「その母親の気持ちはわかる」と言って、逆に鈴木講師に質問してきました。
「お前さ、この世の中に無駄な人は一人もいないって聞いたことあると思うけど、お前は思う?」
鈴木講師は即答しました。
「まあ、無駄な人はいないだろうね。なんでかっていうと、もういるんだもん」
無駄かどうかといったしても、もうそこにいるのだからしょうがないという話をする鈴木講師にその友達は次のようにと教えてくれました。
「そうだよな、いるよなで、それでお母さんがこの世に生を受けた、もう存在しているこの子にもきっと役割があるんだ、この子の力を必要とする人がきっとこの世の中にいるんじゃないかって、それ信じてるんだよ」
鈴木講師はそれを聞いたとき、すごく自分が恥ずかしくなったと言います。
鈴木講師はこれまで働くことは自分のお金を稼ぐことだと思ってきました。
でも、障がいを持った人たちやその母親にとっては「働く」ことの意味が違っていたのです。
彼らが持っている「働く」というのは自分の力が人の役に立つこと、自分の力が人の役に立って相手が喜んでくれれば、そのリターンとして戻ってくるのがお給料だと思っているんだよ、そう教えられた時、自分は「働く」という言葉の意味を考えたことはなかった。
「働く」ことを薄っぺらく捉えて、その言葉を気軽く使いすぎていたことに気付かされたと鈴木講師は言います。
気持ち良く働ける空間を生み出す存在
 自分の力を人の役に立てて喜ばれる、それが働くということだと思っている人たちがこの世の中にいるということが、新鮮であり驚きでした。
自分の力を人の役に立てて喜ばれる、それが働くということだと思っている人たちがこの世の中にいるということが、新鮮であり驚きでした。
「働く」とはどういうことなのかをもっと突き詰めて考える必要があるいうことをその時初めて知った鈴木講師は、障がいを持った人たちに興味が湧くようになりました。
友達と話をしているうちに、そんな人たちがいるなら自分も関われる、やれることがあるのではないかという、その時はボランティアのような気持ちで少しでもやれることはないかという話になりました。
当時の京丸園さんは家族経営でしたから労災すら入っておらず、雇用保険なんてとんでもないという雇用体制で、障がい者雇用ができる状態ではありませんでした。
その状況でもできることはあるかと福祉の人たちに声をかけてみたところ、企業実習のような体験をさせてあげれば良いのではないかという提案を受け、1週間だけであればなんとかやれると考えた鈴木講師は、1週間だけの企業体験、職場体験を受け入れますという形で初めてみました。
障がいを持った人の親御さんたちは「そのチャンスいただけるだけでもありがたい」と言って喜んでくれました。
それでも鈴木講師は、職場の中に障がいを持った人たちを入れることがすごく怖かったと言います。
一緒に働きたくないと言い出す人がいるんじゃないか、障がい者たちがいじめられるんじゃないかなど、何か起こりそうな心配がありました。
だからこそ、多少トラブルがあっても1週間は我慢してと職場には伝えておけばなんとかやれるだろうと、自分に保険までかけて受け入れてみました。
それでやってみて実際何が起こったか、鈴木講師が想像していたことは起こらず、逆に職場の中で障がいを持った人たちに声をかけてくれたり、気遣いをしてくれたりといった行動が生まれました。
例えば、作業場自体が狭かったため、障がいを持った子が後ろを通る時には仕事の手を止めて、後ろの通路を人が通れるように椅子を引いてあげたり,その子が取ろうとしている物をこれかと言って取ってあげたり、何か言いたそうな仕草を見せた時にはどうしたと言って声かけるとか、たったそれれだけのことですが明らかに職場内の行動の変化がありました。
人の優しさとはこのように、みんながその子を気遣って大丈夫かと声をかけたり、これ取ってあげようと言って取ってあげたりなど、自分のことをちょっと横に置いて人のために何かしてあげられることではないか、と鈴木講師は言います。
そして、「たったそれだけのこと」ですが、皆がしてくれたことによって、職場の雰囲気が少し変わったということです。
京丸園さんは高齢者が多い職場で、高齢者は気持ちは強いのでどうしても他人に対して厳しく、ピリピリした空間、ギクシャクしてる空気感がありましたが、それが和やかで優しい空気のほんわか明るい感じの空間になりました。
また、農業というのは手作業が多いので、その時の職場の雰囲気で作業量が大きく変わる仕事であるため、家族や夫婦でやってると喧嘩した日は仕事が思うように進まなかったり、逆に仲が良かったりすると思いのほか仕事が進んだということは頻繁にあると鈴木講師は言い、場の雰囲気が良くなったことで作業量が大きく上がったのを目の当たりにしたということでした。
つまり、健常者に比べたら障がいのある子たちの能力は半分、3分の1程度のレベルですが、彼らに来てもらったことによって場の雰囲気が良くなって、農園全体の生産能力が上げられる可能性があるということです。
やるならギスギスした会社ではなく、気持ち良い会社を作りたい。
勉強会で言われた「どんな農園にしたいのか」という問いに対して鈴木講師は、朝来たら気持ちよく仕事をして、気持ちよく帰れるような、そういった職場を作りたいとも思っていましたから、彼らの力を借りようと考えました。
自分たちの組織を、それ以上に自分たちの農業も変えられるのではないか、それほどの可能性を感じて彼らに賭けてみようと鈴木講師は強く思いました。
問題は障がい者ではなく農業の持続性
 そこで鈴木講師は、とにかくどんな大変でも一年に一人、障がいを持った人たちを雇用するということを自分に課しました。
そこで鈴木講師は、とにかくどんな大変でも一年に一人、障がいを持った人たちを雇用するということを自分に課しました。
働けても働けなくてもまず一人雇用して、その子たちが安心して働けるような職場を作っていけば、きっと組織として自分が理想としているような組織ができるのではないか、それを彼らに託しました。
「どんな仲間たちと一緒に組織を運営していくのか」という問いに対して、障がいを持った子たちと一緒にやろうと鈴木講師は決めました。
当時祖父母と両親そして妻の家族6人に、4人のパートさんで10人の家族経営の農園に、初めて障がい者たちの雇用がスタートしました。
昨年60歳になった鈴木講師は、障がい者雇用開始からちょうど30年となりましたが、現在京丸園さんは107人の組織になりました。
現在鈴木講師が考えているのは障がい者雇用ではなく、「強い農業形態」を作ることだと言います。
それは、次の世代まで事業を引き継ぐというだけでなく、農業が回り続けるための仕組み、作物を作るための「農地」と「耕す人」そして利益を出し続ける「稼ぐ力」をそのまま継承していくこと。
つまり強い農業形態とは持続可能性の高い農業形態のことなのです。
そのために、今農業の中でも外国人の雇用をしたり、若い人たちが新しく農業を始めた、といったニュースもありますが、重要なのはそれらが一時的なことではなく持続的でなければいけないということです。
もし、若い人たちだけで農業をやってたら、その組織の10年後、20年後でどうなるか絵が見えない、と鈴木講師は言います。
これは、組織が若い人であった場合、現在働いている人が将来の働く姿、歳を取って働きにくくなったとしても働きやすい、安心して働き続けることができる仕事、職場であるということが見えないということです。
京丸園さんは現在最高齢者が88歳で一番下が16歳、80代から10代までの働き手がいますから、20年、30年後も組織が続いていくイメージが湧きます。
鈴木講師が目指していたのはこういった持続性の高い組織であり、そのために組織の構造を老若男女、年代別そして男女比で見ています。
特に農業は若い人たちが集まりにくい産業でもあるため、敢えてそのままでは働きづらい、働けない人たちを農業現場に入ってもらうことで柔軟な組織構造を作ろうとしているということです。
障がいを持った人たちの役割は、彼らに働いてもらうことじゃなく「働けない現実を我々に見せてくれること」だと鈴木講師は言います。
働けない人を雇うということは、そのままにしておいたら立ったままの人に給料を払うことになるから、そうならないために必死に考える。
つまりこれは、障がい者雇用の問題ではなく、彼らの力を借りて農業を変えたい、農業の持続可能性の問題を解決するためであり、これこそが障がいを持った人たちと一緒に働く理由だということです。
だからこそ京丸園さんでは、働ける障がい者ではなく、働けない重度の障がい者たちに来てもらい、彼らに少しでも「働いてもらうためには何を変えたら良いのか」を考えて、専用の機械を作ったり構造を変えたりしていきました。
すると、彼らが働けるような場を作った結果、高齢者が集まって高齢者も働けることがわかってきました。
さらに、高齢者が働けるってことがわかってきたら、女性が集まりだした。
そして、女性が集まりだしたら、男性が群がってくる。
一見すごく遠回りをしているように見えますが、結果的に欲しいもの手に入れば嬉しいと鈴木講師は言います。
誰もが働きやすく長く働ける職場
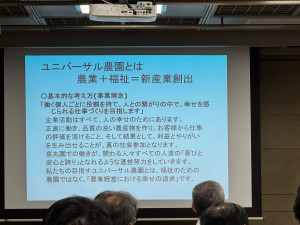 障がいを持った人たちがなぜ障がい者と言われるのか、それは彼らが今の世の中の構造に不具合を感じる人たちだから「障がい者手帳」を持ってもらうことで、周りがある程度配慮してくださいということだと鈴木講師は言います。
障がいを持った人たちがなぜ障がい者と言われるのか、それは彼らが今の世の中の構造に不具合を感じる人たちだから「障がい者手帳」を持ってもらうことで、周りがある程度配慮してくださいということだと鈴木講師は言います。
今人口が減っているのに、障がい者の人たちが増えているという現実がありますが、それだけ「生きにくい世の中になっている」ことだろうとも。
現代には以前にはなかった「発達障がい」というのもあり、以前であれば「変わった子」で済まされていたものが、今は障がい者という扱いにしないと済まされない、一緒にはやれなくなってしまっている実情から考えると、彼らが、引いては人が生きにくい世の中になっているのではないかと鈴木講師は警鐘を鳴らします。
だからこそ、そのままでは働けないと思われている人たち、つまり一番不具合を感じている人たちに合わせて職場を作ってきたこの30年間の結果を踏まえて、「ユニバーサル農業」を提唱しています。
これは、地域に必ずいる高齢者、障がいを持った人たちが農業で戦力になる仕組み、つまり農業のユニバーサルデザイン化していくことで、地域や社会を強くしていこうとするものです。
鈴木講師は30年間の取り組みの中でわかったことを研究論文として様々な方面で発表していますが、その一つが一人一人の勤続年数が長いということを挙げています。
先述の通り現在の京丸園さんは16歳から88、89歳までの人まで働ける職場になっているわけですが、20年以上勤務している人は100人中9人、そのうち障がいを持っている方が4人。
最初に障がい者として入社した方が一番社歴が長く、障がいを持った方がずっと働いていられるということこそが、京丸園さんが長く働ける環境にあることを表していると鈴木講師は言います。
特に農業は作業や技術を次に継承していく産業であり、人が入れ替わることをあまり好まないことから、非常にありがたい効果だということです。
また、京丸園さんには引きこもりの人たちも働いていますが、彼らが家から出てきて働くという現象も起きてきました。
その人たちが初め14人いましたが現在は8名、6名の人たちはまた家に戻ったわけではなく、ここで働けることがわかり自分の適正に合った先へ羽ばたいていったということです。
このように、引きこもりの人たちの活躍の場ができたり、生活困窮の人や犯罪を犯した人たちの更生など、そういう人たちも集まるようになってきたことを考えると、これも障がいを持った人たちが現場にいてくれたことでそういった人たちも出てきやすかったのかもあるかもしれません。
こういった人たちが出てきた構造が理解できるようになれば、引きこもりなどの社会問題もそうならないような仕組みを社会の中に作るための研究材料になるのではないかと鈴木講師は考えています。
働き手に合わせて作られる差別化された商品
 京丸園さんで行われているのは「水耕栽培」という土を使わない農業で、工業的な分野の農業になります。
京丸園さんで行われているのは「水耕栽培」という土を使わない農業で、工業的な分野の農業になります。
そこで主力である芽ねぎやチンゲンサイ、三つ葉などの小さな葉物野菜が作られています。
農業ではイチゴやトマトといった赤いものが儲かると言われています。
その中であえてサイズの小さな葉物野菜を作っているの、イチゴやトマトのように季節性がなく計画生産ができるからです。
季節性が高いものは忙しい時と暇な時が顕著に出てしまいますが、葉物野菜は年間の計画が立てられるので、働く人からしてみると扱いやすい作物だと言えるのです。
計画的な働き方ができるというのは、決まった曜日に休みが取れることであったり、天候に左右されずに一年間の収入がきちんとあるといったことです。
障がいを持った人たちは変化があまりない働き方、仕組みの方が向いている人が多いこともあり、京丸園さんでは葉物野菜の計画的な生産を行っています。
儲かるから作るのではなく、働く人のことを考え、働く人の特性に合ったものを作る。
京丸園さんは障がいを持った人たちと高齢者の方がいるわけですが、畑に出てキャベツとか大根を抜いて担ぐといった作業は現実難しいですから、小さくて軽いもの、座って仕事ができるといった商品を作ることに意味がある。
これは戦略であり、「ユニバーサル農業」は企業戦略だと鈴木講師は言います。
商品開発も戦略的に行われていきます。
例えばトマトが売れるとなると多くがトマトを作りだすので、生産者が値段を崩してしまうという現象が起こります。
京丸園さんは「働き手に合わせた」商品作り、それも障がいを持った人たちや高齢者に向けた商品開発をするわけですが、普通は「儲かる」商品を作りますから自ずと商品自体が差別化される。
他と競争しなくてもいい商品、収益構造を作りたいわけですから、障がいを持った人たちに合わせたデザイン、その人たちが働きやすいものを作れば、その商品は開発時点で差別化されているということです。
障がい者施設の中でも作った商品が売れないという声がありますが、障がいを持った人たちを健常者に寄せた考え方で商品開発しているというのも原因の一つだと鈴木講師は言います。
もっと障がいを持つ人たちに寄せた、彼らにしかできないような商品開発をし、それを差別化として売っていく、これが戦略だということです。
彼らが一般の人たちと戦って勝てないと思うなら、最初から戦わない方がいいわけですから、「戦わない戦略」で経営をしていくべきということです。
働くことで健康と生きがいを創りだす
鈴木講師が提唱しているユニバーサル農業は、農業と福祉を連携させるということではなく、農業と「融合させる」ものだということです。
連携という足し算ではなく、異なる物質が混じり合って新しい物質を誕生させる融合、農業と福祉を融合させて新しい産業を作り出すというのが鈴木講師の夢だと言います。
それが具体的になったのが、足腰が弱ってしまった人のために作った「立ったり座ったりしながら作業する機械」。
足腰が弱ってしまった人が働き場に来た時、これまでは仕事中ずっと座るという選択、働き方をしなくてはいけませんでした。
立っているとふらついてしまうわけですから、普通ならそういう人は座らせて仕事をさせますが、実はそういう人たちはリハビリセンターで立つための訓練をしないといけない人たちです。
しかし、リハビリセンターに行くためには仕事を休み、お金を払ってリハビリを受けるわけですから、そのために座って働くという矛盾がおこっていました。
そこで、そういう人たちが働きながらリハビリができるようにしてあげれば、負担が減るのではないかというところから生まれたのがこの「立ったり座ったりしながら作業する機械」でした。
医師からどれぐらいのペースで立ったり座ったりするのかを聞き、例えば15分経ったら15分座るのが良いということなら、タイマーセットして15分経ったら機械が自動的に低くなって座って作業をし、15分経ったら今度は作業台が高くなるので立って作業をするといったもの。
食べることによって人を健康にするというイメージは湧きやすい農業に、農業現場で働くことでも健康と生きがいが作り出せるとなれば、これは農業の新しい魅力になる。
鈴木講師は近い将来、農業という産業や言葉はなくなり「健康創造産業」に生まれ変わるという夢を持って、チャレンジしているところだと言います。
マイナス要因という思い込みを捨てた先
京丸園さんに来る障がいを持った人たちは、静岡県の最低賃金が700円の時にその半分400円程度の能力評価を受けるような人たちです。
実はこのレベルでは企業の障がい者雇用ではなく、福祉事業所でしか働くことが難しいレベル。
企業もなるべく最低賃金に近いゾーンの人たち、働ける障がい者の人たちを取りたいわけですから、障がい者雇用がなかなか進まない要因にもなっています。
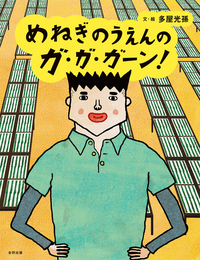 しかし、先述のように京丸園さんが期待しているのは健常者と同じ労力ではなく、「働けない現実を見せる」ということであり、それが彼らの使命だと鈴木講師は考えています。
しかし、先述のように京丸園さんが期待しているのは健常者と同じ労力ではなく、「働けない現実を見せる」ということであり、それが彼らの使命だと鈴木講師は考えています。
京丸園さんがモデルの絵本(『めねぎのうえんのガ・ガ・ガ・ガーン!』合同出版)の中に出てくる人は、最初3時間立っているのがやっと、通勤するのがやっとという体力しかありませんでしたが、7年かけて最低賃金を超えるレベルになりました。
つまり福祉事業所にいる人たちでも、自分たちのビジネスの中で手をかけていければ伸びる可能性があることが証明されてきたと鈴木講師は言います。
働けるゾーンの人たちは企業がある程度障がい者雇用の中で雇い、その上で福祉事業所に行く人たちの中から雇う、そういう新しい社会構造への挑戦が農業には適していると考え、鈴木講師は今も研究を続けています。
従業員数の2.5%は障がいを持った人たちを雇わなければいけない障がい者雇用の法定雇用率がありますが、その達成率は50%でしかありません。
なぜ障がい者雇用が進まないのか、それは企業がビジネスにおいて障害を持った人たちをマイナス要因だと思ってるからだと鈴木講師は言います。
彼らを会社の中に入れることが、経営に対してマイナスになると考えている。
もしそうでないなら、彼らが経営を発展させるプラス要因だとしたら、そんな法律に関係なく雇うはずです。
法律で決められていても雇わない選択をしているということは、それだけ彼らのことを「リスク」だと捉えているということであり、鈴木講師も以前はそうでした。
京丸園さんは今から30年前に最初の一人目を雇用し、だいたい一年に一人ずつ雇用してきました。
もし彼らが本当にビジネスにおいてマイナス要因だとするなら、障害を持った人たちがどんどん増えていけば、京丸園さんは倒産してしまいますが実際はそうはならず、反対に売り上げを伸ばしていきました。
絶対こうなるとは言いませんが、やり方はあるのではないかと鈴木講師は言います。
これからの時代、新しい働き方や新しい組織と言われていますが、実際には今までの延長線であり、それほど変わってないのではないか。
もっといろいろなものにチャレンジしてみても良いのではないか。
障がいを持った人たちや高齢者を加えたビジネス作れば、どのような組織になるのか。
これは、特に農業など人手が集まりにくい産業では、高齢者や障がいを持ったたちを受け入れることによって、これまでとは違う組織構造できないかという提案だということでした。
鈴木厚志社長、貴重なお話ありがとうございました。
また、ご参加された皆様にも改めて感謝申し上げます。