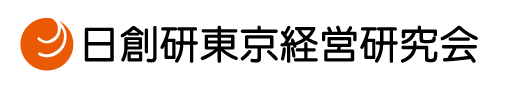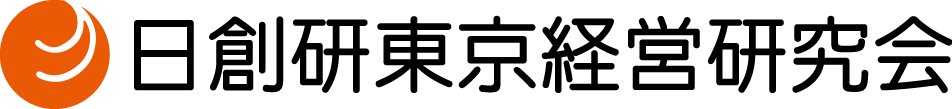今回はIT、AI、DXという近年注目されている経営のデジタル化について、東京、千葉、札幌の各経営研究会の会員仲間が最新の情報と事例を教えてくれました。
まずは、東京経営研究会の辛卿孝さんによるAIを活用したシステムについて教えてもらいました。
顧客に寄り添うための技術
辛講師が代表を務めるソフトシアター株式会社さんは、1997年に設立されたIT関連の情報サービス業で、これまで音羽寿司さん、ボクデンさんなど日創研の多くの会員にシステムを提供しています。
辛講師は企業家養成スクールを25年前に卒業、奥様も企業家養成スクールの卒業生、さらに娘さんも現在業績アップ上級研修に参加してコアコンピタンスを学んでいるということです。
ソフトシアターさんは創業当時富士通の下請け開発を行っていましたが、企業家養成卒業後は自社製品の開発を開始しました。
元々エンジニアである辛講師は、良いものを作れば売れるとばかり思っていましたが、最初思うように商品は売れませんでした。
困った辛講師は認知度を高めようと新婚夫婦が出演するテレビ番組にご夫婦で出演したそうですが、仕事について話したことがほとんどカットされてしまい、期待していたほどの効果を得られなかったエピソードを教えてくれました。
この体験から辛講師は中小企業の経営の難しさを痛感し、現在に至るまで顧客に寄り添ったサービスや提供について考え続けているということです。
過日浜松で行われた全国大会で、田舞代表が1990年代の時価総額ランキングに言及し、当時は世界の上位10社の中に日本企業が7社もあったところ、その後の30年で日本企業は大きく競争力を失ってしまったという現状を語りました。
辛講師も1990年に大学を卒業し、当時の同級生が銀行業界に進んでいたため、日本の銀行が世界をリードしている状況を目の当たりにしてきました。
90年代は製造業が価値源泉とされ、銀行がその資金を提供していましたが、2000年頃からはIT企業が台頭し、価値の源泉が情報と接続性、いわゆるインターネットに移行しました。
現在ではGAFA(現Meta)などの企業が上位に成長し、価値の源泉は知能とプラットフォームに移行していると辛講師は考えています。
時代の変化を映す鏡のように企業のランキングも変わり、AI技術の進展によってその支配がアメリカ、中国の企業に集約されている状況です。
中でも注目されているのが、リン・ウェンフォン率いる中国のディープシークは、アメリカのサム・アルトマンが創業したOPEN AIよりも短期間で大きな成果を上げており、比較的低コストで多くの人材を集めて開発している点です。
ディープシークが開発したAIはアメリカのAIを模倣しているともいわれていますが、合計9億円という低コストでより強力な技術を持っているとされています。
AI市場は今後さらに急成長し、2030年までに市場規模が15倍に達すると予測されています。
ソフトバンクの孫正義氏は、AIが人類の知恵を大幅に超えるとの見解を示し、今後その変革に挑む意欲を表明しています。
また、AIを活用する企業とそうでない企業とでの競争が鮮明になってきており、各企業がこの変化を敏感に捉えたうえでビジネスに結びつけることが重要だと辛講師は言います。
また、近年の企業の価値は知能とプラットフォームにシフトしているわけですが、その多くはデジタルデバイスの普及、特に2008年から始まったスマートフォンの普及に伴い、プラットフォームサブスクリプションから利益を得ています。
2018年頃からサブスクリプションモデルが急増しましたが、代表的なNetflixやAmazon Primeなどのサービスが人気を博しているのは、視聴すればするほど「お得」になるというところです。
サブスクリプションモデルは顧客との契約が始まってから価値が見出され、従来の一回限りの売り切りビジネスとは異なり、顧客データを継続的に取得し顧客の習慣や嗜好に基づいて個別のコンテンツを推奨していきます。
Netflixはその「顧客の習慣や嗜好に基づいた」オリジナル作品に巨額の投資を行い、質の高い情報、つまり顧客が望む情報を提供しているのです。
これは視聴者にとって魅力的であるだけでなく、作品に出演する俳優陣にとっても参加したいと思わせる環境(評価が高い)が整っています。
このように、現在のサブスクリプションモデルには顧客のニーズに寄り添い、深く理解することで企業が成長する流れが見受けられ、自社の顧客との関係を見直す良い機会になるのではないかと辛講師は考えているということでした。
顧客視点と一貫した取り組みがファンをつくる
私たちが企業戦略を構築する際は、AI技術の進展をいかに捉えて実務に結びつけるかが重要だということで、辛講師はその具体的なAIの利用事例を教えてくれました。
音羽寿司さんの例(飲食業)
大阪、京都、神戸に30店舗を展開し、その多くは出前専門店と高級寿司店です。
スタッフ不足やアナログな業務フローといった課題を抱えており、15年前からソフトシアターさんのシステムを導入しています。
特に、「職人気質」な創業者が「属人的」な運営を行っており、コロナ禍においても人材が休むと業務がスムーズに回らなくなるという問題が生じていました。
こうした状況を受けて、我々は3つのAI技術を導入し、出前のための効率的な配車や集客、管理を実現しました。
配車に関しては、10店舗で1日100件の注文があり、そのうち70%は事前に把握されていることが分かったため、迅速かつ効率的に配車を行うシステムを構築しました。
具体的には、電話やアプリでの注文を受けて自動的に配車を組むシステムを導入し、ドライバーがスマートフォン上でルートを確認できるようになりました。
これにより、アルバイトでも配達が可能になり、安心して新しい人材を活用することができるようになりました。
さらに、調理のタイミングを逆算して指示を出すことで鮮度の保持にも配慮、具体的には配車から逆算して料理を投入する最適なタイミングを調理場のタブレットで指示できるようにしました。
こうしたシステムにより、音羽寿司さんは作業の効率化を実現、顧客へのサービス向上に寄与しています。
集客に関する新しい取り組みでは、従来のポイントカードやDM、ポスティングをアプリへと移行し、年間約700万円のコスト削減を実現。
その結果、顧客管理が自動的に行われるようになり、初回顧客や再来店客のデータが連携することで来店回数や金額に応じてファンを育てられるようになりました。
また、3ヶ月以上来店がない顧客には特別なアプローチを行い、忘れられないように新商品や限定商品の案内を送信することで来店促進を図っています。
さらに、家族の情報をアプリで管理、誕生日や記念日にはそれに合わせた特別プランを提案することで、個々の顧客へ最適な価値を提供するようになっています。
これらのプロセスはデジタルAIによって自動で運営されており、顧客との関係を深めるための有効な手段となっています。
ただ、改善を進めていく中で出前の顧客の反応に課題を感じ、配達の動向を分析したところ、システムの導入によってアルバイトでも配達が可能にはなりましたが、配達品質に課題があることがわかりました。
コロナ以降、食事配達サービスの数が増加し、特にUberEatsの人気が顕著であることがわかりましたが、同時に顧客満足度は意外にも低いこともわかりました。
これは単に商品を届けるだけのサービスであるため、多くの配達員がその食事に対して何の思い入れも持っていないということが原因でした。
調査したところ、ピザ店の顧客満足度が高かったのですが、これはピザ店の多くが自店舗で調理した熱々のピザを直接届けているからでした。
そこで、音羽寿司さんでは具体的な対応策として、配達時にお客様に対して感謝の言葉を添えることを試みました。
例えば、届ける際に以前の注文の感謝を述べたり、他の店舗での購入に対して感謝を述べるなど、一言感謝やおもてなしの心を伝えることで配達サービスの品質は高まりました。
このように、デジタルとアナログを融合させることで、お客様の嗜好や気持ちをきめ細かく汲み取り、より良いサービスを提供できるようになっています。
現在は注文受注AIを活用し、配車から調理指示、配達完了までの一連の流れを自動化し、その結果得られた情報を基に顧客分析を行いマーケティング戦略を立てていくことで、熱心なファンを育成するアプリシステムを構築していくと辛講師は言います。
辻釣船さんの例(釣船店)
辻釣船さんは、愛媛県伊方町の宇和海で鯛釣りやイカ釣りを専門とする釣り船屋です。
このお店は、父親が宇和海において40年間営んでいた養殖業をコロナ禍で廃業、事業を売却したところから始まります。
辻さんは2000万円でこの会社を売却、1500万円を船の購入、500万円をIT投資に充てました(IT導入補助金を利用し、実質150万円でシステムを構築)。
さらに、釣り業界の一般的なイメージを刷新して独自の釣船店とするために6つの「やらないこと」を設定しました。
①釣果を追わない。思い出になる宇和海の1日にする
②釣り熟練者を追わず、釣りを好きになるような初心者を追う
③釣船の船長や漁業関係者にある高圧的な態度をしない。愛媛のマルブンさんをベンチマークし、徹底的に接客待遇を導入する
④人は雇用しない。完全にワンオペでできる仕組みを作る
⑤電話は使わない。文字で残るLINEを使用し、オンタイムの返信を心がける
⑥乗船客を1人にさせない。釣り場につくまでに乗船者同士を仲良くさせる場を作る
2021年3月に創業しましたが、開始当初は予約が月に3件しか入らず苦戦しました。
そこで、アプリ開発を進め、InstagramやLINEを通じてマーケティングを行いました。地道に顧客の写真をアップしたり、チラシ作成にも取り組みましたが、最初は反応が薄いものでした。
それでも、温かい手作り弁当を提供したり、3回来てもらうために段階的に割引価格で利用できるクーポンを配布するなど、顧客満足度を高めるための工夫に取り組み続けました。
結果として予約件数は月3件だったのが307件にまで増加しました。
1年間で600人の顧客を作るという計画を立て、当初は全く集まらなかったところ、結果的に3ヶ月過ぎてから急に増え始め、当初の目標を達成することができました。
また、パレートの法則(2:8の法則)どおり600人のうち20パーセント、つまり100人から120人ぐらいは熱狂的なファンが占めていて、何度も利用してくれるリピーターになってくれました。
これだけ顧客が増えると対応しきれないのですが、最初からワンオペで回せるようにDX化、アプリによる回数券の購入から事前決済、そして乗船予約までアプリで顧客側が行うようにしていましたから、顧客が増えても何の支障もなく一人でやっていけました。
これは、コロナ禍の逆境を経営理念が救い、DXとAIがマーケティングと管理を助けてくれるという成功事例だと辛講師は言います。
この2つの事例を振り返ってみると、冒頭で話した通りお客様にどれだけ寄り添えるかというのが、これからのビジネスの大きなテーマであると辛講師は言います。
儲かっている企業は、このことを常に考えています。
解約させない、あるいは口コミで広げさせる、ということも、その根本はお客様の気持ちを理解することに答えがあります。
辻釣船さんも、お客様に「思い出になる宇和海の1日にする」ために温かい手作りのお弁当を用意することにしたことが、ファンがついてきた理由の1つです。
そういったことが、全て繋がっている、顧客に対する姿勢が一貫しているということが非常に大事だと辛講師は言います。
DXによって自社のビジネスをどのように変革していくかというのを考える際、顧客を理解し、顧客起点でビジネスを変革することこそが大事であり、顧客視点で正しいことをやっていれば、どこかでバズる時があるということでした。