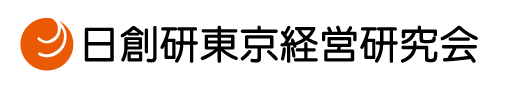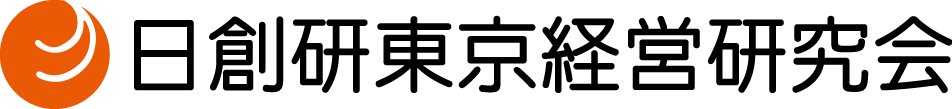続いて株式会社ストーンシステムの松丸元康社長から、仕事の効率を上げるための生成AIの上手な使い方について教えてもらいました。
生成AIの強みと弱み
ストーンシステムさんは、証券会社やFX会社、暗号資産取引所向けにシステムを開発されているのですが、最近は生成AIについての質問や勉強会の招待が増えてきたと松丸講師は言います。
松丸講師は必ずしもその専門家ではないということですが、IT業界で長年活動していることから、仕事上で生成AIに関連する技術を活用している部分もあるということです。
例えば大手電話会社と協力し、災害時におけるAIの実証実験を実施したこともあり、この時は被災者への適切な情報提供には生成AIの利用は難しいとの結論を得たということです。
また、技術者向けのeラーニングツールでは、生成AIのチャットボットを組み込む取り組みも行っていて、それはボットにマニュアルを読み込ませることで、利用者がつまずいた際に迅速に解決策を提示する機能を持っているということです。
さらに、大学との連携で過疎地域における効率的なバス運行の方法を模索していて、利用者の依頼に応じてバスのルートを最適化したシステムの開発も行ったということです。
生成AIとは自然な文章を生成したり、説明文から新たな画像や動画、音声を作成する技術ですが、ストーンシステムさんが生成AIの利活用によるさまざまなプロジェクトに取り組む中でわかった、従来型のAIと生成AIの違いについて教えてもらいました。
従来型AIが主に定型業務を得意としているのに対して、生成AIは主に非定型業務に特化しているところだと松丸講師は言います。
具体的には、従来型AIが顧客データの分析や予測モデルの構築、パターンマッチングが得意である一方、生成AIはクリエイティブな表現を行うので、ビジネス文書の作成やコミュニケーションの効率化、特にマーケティングで強みを発揮するということです。
ただ、生成AIを使用する際にはいくつかの注意点があり、最も注意すべきは出力には誤りが伴うことがあるということです。
生成された情報の正確性に注意し、専門家の確認を求める必要があることや、個人情報や機密情報の取り扱いにも留意すること、そのためのリスクヘッジとして社内専用のシステムの導入も考慮すべきだということです。
さらに、生成AIを用いたコンテンツ作成には著作権や法的な問題が伴う可能性があり、特に生成したコンテンツを商業目的で使用する場合には注意が必要です。
まとめると、ビジネスでの生成AI活用においては、事実に基づかない出力(ハルシネーション)があるという認識が必要であること。
さらにアメリカや中国由来の技術であるため、その地域の文化が反映されていることから偏見やバイアスの問題にも注意して使用しなければいけないということでした。
そして、生成AIの利点を活かすためにはライセンスやセキュリティの観点からも適切に利用する姿勢が求められるということでした。
生成AIの上手な使い方
松丸講師は、以上のようなデメリットや注意事項を認識した上で使用すれば、生成AIはビジネスにおいて非常に役立つと言います。
ただ、生成AIは先述の通りクリエイティブな表現を行うことに長けたものなので、ビジネスで活用する際は次の3つの基本事項に則って使用すべきだということです。
一つは「前工程で利用する」というもので、例えばシステム開発であれば生成AIがコーディングをしてくれる、つまりシステムを作ることができるのですが、1回で間違いや誤りのない完成形を作れるわけではないので、例えばプロトタイプ(試作品)を生成AIで作り、それを元に開発を進めていくといった使い方です。
次に「責任は使用者が負う」というもので、当然ですが生成AIの使用にあたっては使用者が責任をもって扱うということであり、ビジネスで活用する上では必ず生成AIで作られたものを監視・監督する人が必要だということです。
3つ目は「学習データとしての提供を避ける」ということですが、これは機密情報などを与えたようなシステムを作ると先述の通り様々な問題を孕んでいることからかなり危険であるということです。
この基本事項を踏まえて、生成AIをビジネスに活用するのに適したタスクとして松丸講師は、以下の3つのタスクを挙げました。
①正確性が必要ないタスク
②人間が行うと負担が多いタスク
③状況の整理が必要になってくるタスク
ビジネスにおいてこの3つのタスクに関わるものとしては「マーケティング」があります。
マーケティングの主な作業は調査・分析であり正確性も必要ですが、市場規模を調べる段階ではそこまで細かい数字は求められません。
さらに、おおよそのニーズを調べる時は生成AIがターゲットの視点に立って回答してくれるので、非常に便利です。
今まではアイデアが生まれても、市場規模やニーズを調べようとしても詳しい人に聞いたりユーザーに直接尋ねるしかありませんでしたが、生成AIであればアイデアの内容と調べたい部分を投げかけるだけで、すぐに調べて答えてくれます。
ビジネスシーンにおけるChatGPTの使い方の具体例ということで松丸講師は以下の3つを挙げて教えてくれました。
① 自社のSWOT分析を行う
② フェルミ推定で市場規模を試算する
③ 自分だけのオリジナルのAIを作ってみる
① 自社のSWOT分析を行う
ホームページや会社案内、経営理念といった情報を与えて、ChatGPTに自社を分析してもらうというもの。ホームページや製品サイト、求人サイトなどの情報を与えると、自社の強みや弱み、機会や脅威を分析してくれます。
こういった自社や自社を取り巻く環境を俯瞰的に見るということが難しい部分こそ、ChatGPTを使って第三者的な視点で見るというこことが非常に大事で、ChatGPTはさらにアドバイスまでしてくれます。
② フェルミ推定で市場規模を試算する
フェルミ推定とは、実際に調査することが難しい数量や規模を、最低限の知識と論理的思考力を使って短時間で推定する手法です。
つまり、最低限の知識から目的の規模や数量を推測するというもので、新しいアイデアの市場規模のような「おおよそ」の大きさが知りたい時に求められますが、その人の知識量が影響することから生成AIにうってつけの試算方法です。
③ 自分だけのオリジナルのAIを作ってみる
会社のその経営理念や、インタビュー記事などの情報を与えることで、その人の代わりに相談に乗ってくれるAIや、金融に詳しい生成AIを作ることもできます。
例えば社内にあるマニュアルや様々な情報を与えておくことで、情報を探さなくても作ったAIに聞くだけで答えてくれます。
生産効率の悪いところにAI
現在はChatGPT以外に目的に応じた生成AIがあり、ビジネスシーンに応じて使っていくことができます。
松丸講師はその中でも「ガンマAI」と「ボルト・new」という生成AIを紹介してくれました。
ガンマAIというのはプレゼン資料を自動生成してくれるツールです。
プレゼンテーションで重要なのは起承転結ですが、実は生成AIが得意とするところで、AIが起承転結を組み立ててくれるので、あとは画像などの細かいところだけを変えていけば良いという優れもの。
松丸講師曰く、80点ぐらいのプレゼン資料が簡単に作れるということです。
ただ、これの上手の使い方は、いきなりその100点の資料を求めないことだとも松丸講師は言います。
自分で起承転結が整った資料を作るには1本だけでもそれなりの時間が必要ですが、生成AIの良いところは50点、60点ぐらいのものを短時間で作ってくれるところ。
つまり、これまで1本作っていた時間で異なるものを2本、3本と作ることが可能で、こちらはその中から選んで仕上げていけば良い。
生成AIは、そういったこれまで手間になっていた部分を任せることで、使う側の選択の幅を広げより質の高いものを生み出す、という使い方をするのが良いということでした。
次に「ボルト・new」という生成AIですが、これはウェブアプリケーションであったり、ウェブサイトのプログラミングをしてくれるツールです。
例えば会社の求人サイトを作成したいという時、作りたいと考えるイメージや情報を入力するだけで短時間で作り上げてくれるというものです。
「働く人の顔が見えるようにして働きやすい環境であることをアピールしてください」や、現在のホームページや参考にとなるサイトの情報などを入力すると自動でコーディングをしてくれます。
出来上がったものに対して、変えたいところの指示をさらに伝えていけば、瞬時に手直ししてくれます。
ストーンシステムさんでもこのボルトを使って新しいシステムを作っていると松丸講師は言います。
顧客が要望するシステムを作る上で一番重要なのが「要件定義」いう、言わばシステムの基本仕様をまとめた設計図作成ですが、顧客が作りたいものがなかなか伝わらないことから非常に時間がかかります。
その要件定義においてこのボルトを使ってやりたいことや要素の配置などを具体的な形にすることで、頼む側と作成する側が目指すべきものを確実に共有することができ、しかも短時間で何度でも行えます。
ホームページ制作も同じで、サイトを作りたいと考えてもイメージが湧いていないという時がありますが、思いつくキーワードや情報をAIに与えてとりあえず作ってもらう。
出来上がったものに対して、違和感を感じる部分に対して修正を何度か繰り返すことで、次第に自分が作りたいホームページのイメージが湧いてきます。
これを実際に人がやろうとすると大変な時間と労力が必要で費用も馬鹿になりませんが、現在はまだ生成AIを制作の前段階で使用しているところは少なく、それだけ非効率な生産が行われているということです。