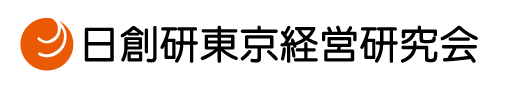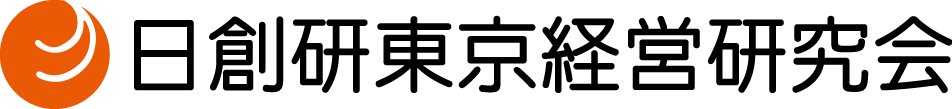2025年10月20日、東京経営研究会10月例会にて、株式会社ココトモファームの齊藤秀一代表取締役にご講演いただきました。「理念から生まれるビジネスモデル」というテーマのもと、農業×福祉×商業×工業を融合させた独自の6次産業モデルと、「誰一人取り残さない居場所づくり」を実現する経営の在り方について、貴重なお話を伺いました。
障害を抱える家族と共に生きる経営者の原点
齊藤代表ご自身もADHD(発達障害)をお持ちで、ご家族にも障害のある方が複数いらっしゃるという環境に置かれています。「家族の気持ちがわかる」――この原体験こそが、齊藤代表の理念経営の原点となっています。
齊藤代表は現在2社を経営されています。一つは障害福祉に特化したシステム「ハグ」を全国の多数の施設に提供するIT企業。もう一つが今回ご紹介いただいた株式会社ココトモファームです。愛知県犬山市の認定農業者として、米の生産販売とグルテンフリーバームクーヘンの製造販売を行い、2023年には就労支援B型事業所「ココトモワークス」を立ち上げ、農業と福祉、商業、工業を組み合わせた持続可能なビジネスモデルを構築されています。
同社は「ディスカバー農山漁村の宝」に選定され、総理官邸で総理とお話しする機会を得たほか、「ノウフクアワード2024」でグランプリを受賞するなど、農業と福祉を連携させる取り組みで注目を集めています。設立から数年で高い収益性を実現し、急成長を遂げている企業です。
「居場所」の必要性から生まれた事業構想
齊藤代表がココトモファームを立ち上げた原点には、「居場所」への強い思いがあります。子供の頃から「社会に自分の居場所がない」と感じていた齊藤代表は、もともとIT企業を立ち上げ、その中で障害福祉のシステムを開発する中で「支援」の本質を学びました。
「支援というのは、誰のために必要なのか。本人が少しでも暮らしやすくなるために支援をしていく。みんなと同じになることが目的ではない」――この気づきが、齊藤代表の経営哲学の核となっています。
障害福祉の現場で子どもたちと関わる中で、齊藤代表は重要な発見をされました。「障害はなくそうとか消そうとすると苦しくなる。受け入れていくしかない。ただ、マイナスがあるという受け入れ方よりも、見方を変えれば、他の人と同じことはできないけど、他の人と違うことができる。それを肯定的に受け取るために居場所が必要」というのです。
さらに、子どもたちの自己肯定感を高める以前に、お母さんたちの自己肯定感が極めて低いという現実にも直面されました。「自分のいいところを書き出してください」と言っても、なかなか書き出せない親御さんがいる。お母さんたちが「先が見えない」「この子が大きくなったらどうなるのか」と不安を抱え、自分を責めている。そんな親御さんの居場所も必要だという思いが、事業の構想を広げていきました。
農福連携の壁を乗り越える「農商工福」6次産業モデル
転機となったのは、農福連携推進フォーラムへの参加でした。農業も大きな課題を抱えています。毎年、新規就農者を上回る数の離農者が出ており、農業人口の減少、耕地面積の減少、耕作放棄地の増加が深刻化しています。一方、福祉側も働く場所の確保が課題です。この両者をつなぐ「農福連携」に可能性を感じた齊藤代表は、当初、子ども向けの農福連携型放課後等デイサービスを立ち上げました。
しかし、やってみると大きな壁にぶつかりました。まず、農業は想像以上に大変で、福祉も一生懸命やる中でプラスアルファの農業は職員の負担が大きすぎる。また、小規模では収益性がなく、施設の経費が増えるだけ。さらに決定的だったのは、「そもそも将来農業で働きたいというニーズがない」という現実でした。お母さんたちは子どもの将来を心配しているものの、「うちの子を農家にして自立させよう」と思う親はいない。子どもたちも「将来YouTuberになりたい」とは言っても、農業をやりたいとは言わない。
この壁を乗り越えるために齊藤代表が考案したのが、農業と福祉をそのまま連携させるのではなく、その間に「商業」を入れ、さらに製造の「工業」を加えた「農商工福連携」の6次産業モデルです。
具体的には、第一次産業(農業)で米を生産し、第二次産業(工業)で加工してバームクーヘンを製造、第三次産業(商業)で販売する。1×2×3=6次産業です。この仕組みによって経済を回し、その経済の中に農業と福祉を組み込むことで、両者を持続可能にしていく。「社会の一員として農業と福祉を位置づける」というのが、ココトモファームの考える農福連携6次産業のコンセプトです。
6次産業化することで、もう一つ重要なメリットが生まれます。すべての障害のある方が農業に向いているわけではありません。むしろ向いていない人の方が多い。しかし6次産業であれば、農業に向いている人は農業、二次産業の製造に向いている方は製造、販売に向いている方は販売と、多様性のある居場所を作ることができるのです。
一次産業:大規模な米づくりと体験価値の創造
ココトモファームの一次産業は、広大な田んぼでの米生産です。しかし、単に米を作るだけではありません。農業体験や農業用ドローンの体験など、「体験価値」を付加しています。
最近の農業機器は驚くほど進化しており、田植機はGPSで自動走行し、農業用ドローンは空を飛んで農薬散布を行います。「本当にテーマパークのアドベンチャーのような感じになる」と齊藤代表。この体験が子どもたちに大人気で、農業の生産価値だけでなく、教育価値や食育、さらには農業観光としての付加価値を生み出しています。
二次産業:グルテンフリーバームクーヘンが生む高付加価値
生産した米を加工して作るのが、グルテンフリーのバームクーヘンです。6次産業化でよくある失敗パターンは、「作ることはうまくできても、売ることができない」というもの。作るプロセスと売るプロセスは全く異なるため、売るための仕組み作りが必要です。
ココトモファームでは、上質な箱を作り、パッケージにこだわり、ギフトとして喜ばれるような商品づくりを徹底しています。特に注目を集めているのが「縁バーム」という商品です。
犬山には国宝・犬山城があり、その城下町に縁結びの神様として知られる三光稲荷神社があります。若い女性が多く訪れる人気スポットです。そこで「縁結びの『縁』」と「バームクーヘンの『円(丸い形)』」を掛け合わせた「縁バーム」を開発。簡単に言えば「インスタ映えする商品」です。
城下町に来て、縁結びの神様にお参りをして、この縁バームを持って写真を撮る――何も宣伝しなくても、SNSでどんどん拡散されていきました。決して安くない価格設定にもかかわらず、大変好評で、多くのお客様に支持されています。「作っても作っても売れていく」状態が生まれました。
この「売れる仕組み」こそが、二次産業で付加価値を上げる戦略です。
三次産業:地域と共生する販売戦略
三次産業の販売では、地域との共生を大切にしています。犬山城下町で最初にオープンした店舗は、シルバー人材センターとの共同店舗でした。
シルバー人材センターの会員であるおじいさん、おばあさんが自分たちで作った野菜や手作りの小物を販売している店舗でしたが、若い女性客が多い城下町では客足が伸びず、家賃を払うのも大変という状況でした。そこで「一緒にやりましょう」と提案し、店舗の半分を借りて、のれんやキャッチコピー、縁バームのポスターや看板を設置し、おしゃれな雰囲気に変えました。
すると不思議なことに、若い女性がどんどん入ってくるようになり、おしゃれな店舗で見ると手作りの小物も野菜もおしゃれに見えてきて、シルバーさんの商品もよく売れるようになったのです。シルバーさんも縁バームを買ってくださり、お互いがウィンウィンの関係を築く「老人福祉と農業の農福連携」が実現しました。
さらに、農福連携全国大会では、中部電力の特例子会社である中電ウィングファームと連携。知的障害の方が丁寧に作る高品質なイチゴと、愛知県のお米で作ったバームクーヘンを組み合わせた商品を開発するなど、企業との連携も積極的に進めています。
聴覚障害者が輝く「サイレントストア」の挑戦
ココトモファームの最も象徴的な取り組みの一つが、全員が聴覚障害者という店舗の運営です。この店舗は福祉施設ではなく、一般就労です。障害者雇用でもありません。聴覚障害で耳が聞こえず、話すこともできない方たちだけで運営する店舗なのです。
きっかけは、聴覚障害者だけでハウスクリーニング会社を東京で経営されている方との出会いでした。その方は「障害があるという理由だけで安く働かされる」「全く同じ仕事をしても、普通の料金では仕事をもらえない」「やらせるだけやらせてお金を払ってくれない、ただ働きをさせられる」といった苦労をされてきました。文句を言いたくても、聞こえないし話すこともできないため、泣き寝入りするしかなかったのです。
その方が犬山に遊びに来た際、齊藤代表の著書を読んで「ココトモファームで働きたい」と希望され、まずは店舗で販売研修を受けることになりました。一生懸命に商品を覚え、箱を折り、品出しをする姿に、スタッフも感動しました。LINEでのやりとりで「今までは最後まで話を聞いてくれないことが社会にいっぱいあった。でも、ココトモファームのみんなは優しくて、最後まで話を聞いてくれて、一緒に考えてくれる。生まれて初めてのことで本当に嬉しい」というメッセージをいただきました。
しかし、実際に店頭に立つとトラブルが起きました。声が聞こえないため、お客様が話しかけても気づかない。お客様からは「無視された」と感じられてしまうのです。バッジをつけたり、筆談ボードを用意したりと工夫しましたが、どんなに頑張っても「普通のスタッフと同じ」にはできませんでした。
そこで、店舗メンバーと本部メンバーが一緒に考え、逆転の発想が生まれました。「こちらがお客様に合わせるのではなく、お客様に合わせてもらう」――「サイレントストア」というコンセプトです。筆談、ジェスチャー、手話でやりとりする「話さないお店」としてブランディングし、看板やのぼりを作り、「言葉がなくても心は通じる」というメッセージを打ち出しました。
最初は名古屋駅のナナちゃん人形近くの小さなスペースでスタート。全員聴覚障害者で、呼び込みもできないため、ジェスチャーで手招きをするだけ。すると不思議なことに、お客様も誰も話さなくなりました。お客様が一生懸命筆談したり、ジェスチャーしたり、最近のドラマの影響で手話を使う方も増え、誰も話さないのにみんなニコニコしながら商品を購入していく光景が生まれたのです。
他の出店者と比較しても際立った売上を記録し、大ブレイクしました。この光景を見て涙を流す方も多く、24時間テレビのドキュメンタリーにも取り上げられました。
経営理念「ここで友達になろう」が生む世界観
ココトモファームの経営理念は「ここで友達になろう」。ビジョンは「誰一人取り残さない居場所を作る」。バリューは「ワクワクが人を成長させる」です。
特に印象的なのは、ココトモファームのロゴです。SDGsのロゴのようにいろんな色があり、いろんな大きさがあり、いろんな形がある。齊藤代表は「障害というのは決して劣っているのではなく、違っているだけ」と強調します。違っているからこそ、できないところは得意な人が支え、その代わり活躍できる出番を作っていく。
例えば、聴覚障害者の店舗も100%聴覚障害者だけでやると、商品の入れ間違いのクレームがあった場合、聞くことも話すこともできないため対応ができません。そういう時は健常者のスタッフが対応する。農業の大変なこと、暑さや日射病の危険がある作業は全て健常者が行い、その代わり障害のある方には活躍できる場所を作る。
「学んだことを行動に変えて実践していく。違っているからこそお互いを支える」――これが「ここで友達になろう」という理念の実現なのです。
齊藤代表は質疑応答で、理念浸透の方法について「理念朝礼は一切ない」と明言されました。その代わり、「思いを伝える場面を増やす」「理念体系で世界観を作り、こういう世界の中で我々が働いているんだよという部分から理念を浸透させる」というアプローチを取られています。理念を言葉で教え込むのではなく、世界観として視覚化し、体感してもらうことを重視されているのです。
売上目標のない会社が実現する高収益経営
ココトモファームには「売上目標がない」という驚くべき特徴があります。ただし、数字は全員がリアルタイムで見られるようになっており、「今日はこんなに売れた!」と喜び合うことはあります。
では何を指標にしているのか。齊藤代表は「KPIの作り方」を重視されています。KGI(最終目標)に至るためのKPI(重要業績評価指標)として、「お客様の笑顔」を定量化したり、SNSのフォロワーをどれだけ増やすかを設定したりしています。経営プロジェクション(事業計画)を作りながらビジネスモデルを考え、KPIで構成していくと「いつの間にか売上がついてくる」というやり方です。
社員は「売上を上げよう」とは全く思っていないけれど、KPIで行動していると結果として売上につながる――この仕組みが、高収益を実現しているのです。
また、齊藤代表は日本創造教育研究所(日創研)の研修を積極的に活用されています。起業家養成スクール、社長塾、マネジメント養成コース、業績アップ上級コースなどを継続受講され、「新しい時代の社長学」も受講予定です。特にSGA(成功の技術を学ぶ研修)は全社員が受講し、コアメンバーへの昇格条件としています。
質疑応答では、ある会長から「思いへの共感が大事」という指摘があり、齊藤代表は「まさにその通り。バームクーヘンの一つひとつに、いろんな人が関わり、いろんな思いが込められている。みんなが思いでバームクーヘンを作っている。それが当社の商品」と答えられました。
地域創生と持続可能な社会への挑戦
ココトモファームが目指すのは、単なる福祉事業や農業事業ではなく、「地域創生」です。現在、全国の放課後等デイサービスに通う子どもの数は増え続けています。子どもの数は減り続けているのに、福祉支援を受ける子どもは増え続けている。「この子たちが大きくなったらどうするのか」という問題は、社会全体の課題なのです。
齊藤代表は「親御さんが悩んでいるのは、この子が私より先に死んでくれればいい、面倒を見てくれる人がいない、一人で生きていけない」という切実な声を聞いてこられました。残念ながら、追い詰められた親が子どもを道連れにする事件も起きています。
「住む場所があり、そこで働く場所があり、そこで社会とつながる場所があれば、それが結果として地域創生につながっていく」――齊藤代表の挑戦は、福祉という枠を超えて、持続可能な地域社会の創造という壮大なビジョンにつながっています。
最後に、ココトモファームの店舗は「多様性がある場所」として、聴覚障害者だけでなく、様々な障害のある方が一般就労で働いています。「違っているからこそお互いを支える」という理念が、日々の現場で実践され、お客様にも感動を与え、社会に新しい価値を提供し続けているのです。
参加された経営者の皆様からは、「理念を視覚化する世界観づくりの重要性を学んだ」「問題の裏側に可能性を見出す視点が素晴らしい」「KPIの設定の仕方が参考になった」「多様性を活かす経営モデルに感銘を受けた」といった感想が多数寄せられました。
齊藤社長には、理念経営の本質と、それを実践することで生まれる持続可能なビジネスモデルについて、具体的な事例を交えて丁寧にお話しいただき、誠にありがとうございました。参加者一同、大きな学びと刺激を得ることができました