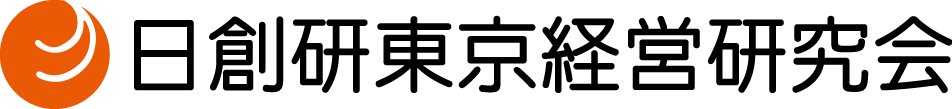今回は感動創造委員会(長谷川剛 委員長)による例会で、現在のコロナ禍における東京経営研究会の会員企業の取り組み事例を発表してもらいました。
事例1. 株式会社マルチョウ
世界に誇れる日本の服つくりを目指して
まずは長谷川委員長が代表を務める株式会社マルチョウさんです。
マルチョウさんは墨田区でアパレルのOEM製造をされており、有名ブランドへ国産100%の製品を納めています。国内5拠点5工場で製造、グループ総数140名で操業しています。
現在日本の衣料品自給率は2%しかなく、それだけに国産製品を守るためにマルチョウさんは国内の工場をグループ化して盛り上げようとしています。マルチョウさんの経営ビジョンにはその具体的な取り組みが掲げられています。
経営ビジョン「世界に誇れる日本の服つくり」
縫製技術の承継
産地工場の発展
地域社会の繁栄
私達は、Made in Japan を守り続けます
しかし、日本国内の市場は減少し続けており、国内だけでは守ることはできません。そのためマルチョウさんは世界に目を向け、海外ブランドへ積極的にアプローチし、日本の技術を世界へ売り込んでいます。
業界の危機
今回の新型コロナウイルス感染症拡大によってアパレル業界はかつてない窮地に立たされていると長谷川さんは言います。
衣料品小売業の経営破綻が世界で始まり、連鎖的に関係の製造工場が危機に瀕しています。
そもそもアパレルのビジネスモデルは根本的な見直し、EC化へのシフトが必須とされながらもなかなか変わることができずにいました。そんな中での今回のコロナ禍によって、大幅な売り上げ減少が起こればアパレル破綻ラッシュとなってしまうということです。
先述の通り、日本の衣料品自給率は30年前50%だったものが現在2%にまで下がり、同時に市場も20年前の3分の2まで縮小しました。
一方でファストファッションの台頭によって、業界内で激しい価格競争が起こり、価格を下げるために過剰出店、大量発注を繰り返したことによって市場は供給過剰に。そのため頻繁にセールが行われ、さらに行き場を失った商品は中古業者に引き取られていく。その結果客単価は30年前の半分にまで下がりました。
このビジネスモデルが30年間ほぼ変わることがありませんでした。
そこへコロナ禍という予想だにしなかった事態が起こり、奇しくもこのビジネスモデルが変わらざるを得なくなってしまいました。
商品は作れない、売れない、買いに行けない。
ファッションは楽しむもの、好きな服を着て幸せに、元気になるものだったのに、それができなくなってしまったのです。
それどころか、以前は当たり前に手に入れることができたマスクでさえ、市場から姿を消してしまいました。
マスクの副産物
世界中でマスクが不足し始めたことから、マルチョウさんでは社員さんの家族や仕入れ先、顧客のためのマスクを作り始めました。
国産の高級衣料品を作ってきましたから、マスクを作ることは決して難しいことではなかったわけです。
今期の売り上げは激減するであろうことは目に見えていましたが、このマスク不足という事態においてこれまでになく縫製業の必要性が高まり、「今こそ恩返しをする時」と考え、各地域や関係者に対してマスクを寄贈することにしました。その数2万5千枚、お金の問題ではない、それがマルチョウさん全社員の総意でした。
ところが、蓋を開けてみればそれ以上の「副産物」がマルチョウさんに次々と生じました。
一つは社員さんのロイヤリティーの向上、今まで以上に熱心に仕事に取り組んでくれるようになったことでした。
寄贈したことによって様々なメディアに取り上げられるようになり、誇らしく思えると同時により良くしたいという思いが強くなったのです。寄贈された人からいろいろな形で感謝されることで、仕事に対する喜びや会社に対する気持ちが高揚していったのです。
これは同時に顧客や消費者の認知度がアップ、信頼が高まることでファンができました。
関係する地域や企業に対して寄贈、それが緊急時の需給バランスが崩れた製品であったので、称賛と共に受け入れられました。
その中でも功を奏したと言えるのが自治体からの信頼とお客様からの注文依頼(マスクOEM)でした。
地域のこど達からの感謝は従業員さんを感動させ、大きな原動力にもなりました。
このことからさらに客先だけでなく消費者の声も直接聴けるようにもなりました。
マスクの性能についての意見をたくさんもらうことになり、そこから大きな発見があったと長谷川さんは言います。
消費者の意見というのは「個人の意見」ですから様々な声があるわけですが、とりわけて特徴的だったのが「真逆」の意見が多かったということです。
大きい・小さいから質感に至るまでそれぞれの意見があり、そのことからこれまでの「正しいか間違っているか」ということだけでなく「何が最善か・拘りか」ということ、つまり直接声を聞くことで使う人にとってベストなもの、本物を作ることができるということです。
マルチョウさんの経営理念は「人を幸せにする、最上の服づくり」ですが、これをマスクの寄贈を通して全社で共有することができました。
一部の人、仕事の一部のことではありますが、人を幸せにするということを実感することができたのです。
また、「縫製技術の承継、産地工場の発展、地域社会の繁栄、私たちはMade in Japanを守ります」という大きなビジョンもマスク寄贈という取り組みによって一歩前進することができました。全社で取り組み体験したことでビジョンをしっかりと認識することができました。
新しい業界の発展に向けて
そして予想だにしなかったのがECサイトの立ち上げでした。
当初は寄贈するものなので小売りはしないとしていたのですが、多くの要望が寄せられたことからECサイトでの販売が決まりました。
将来的に行うことを考えていたところでしたが、思いがけずスタートすることになりました。
始めたことで小売の課題が見え、また消費者の声や企業顧客とは異なる満足度などたくさんの気づきがありました。
このことから、振り返ってこれまでの仕事ぶりを見直すことができ、将来の「ファクトリーブランド」に向けた大きな前進となりました。
また、マスクの寄贈を通してこれまでのアパレル関連企業ではない異業種企業や自治体とのビジネスも始まりました。
これまでお付き合いのあった方々も「アパレル」ということでマルチョウさんを捉えていましたから、現実のマスク製造を見て捉え方が変わっていきました。
自社のオリジナルマスクの依頼から、作業用や記念品としての衣類の製作、さらに卸売の相談も。
これらのことから、これまでの「国産の服作り」のメリットをそのままに、これまでとは違うステージでの製品の提供の可能性が生まれました。
コロナ禍のマスク寄贈という行動が、それまで課題であった「アパレルに依存しないものづくり」の基盤を作ることにつながったのです。
マスク寄贈を通して様々な気づきや変化が起こりましたが、混乱が始まった当初は「物を売ることができない」という状況の中、業績は急速に悪化し不安に苛まれ続けたと長谷川さんは言います。
マスク寄贈を決めた時も「本当に正しい決断だろうか」と自問自答を繰り返しました。
そんな長谷川さんを励ましてくれたのが寄贈した先から送られてくるたくさんの感謝の言葉でした。
そんな一人ひとりからの感謝と応援を受けて、長谷川さんとマルチョウさんは決意を新たに動き始めました。
「ファッションは人を幸せにして、元気にすることが出来る。コロナで疲弊した心をファッションで明るくしたい。ファッションの力を信じます。
私達の役割は、そのアパレルを新しいものづくりで支える事。僅か2.0%しか存在しない国内工場で必要なものを必要なだけ、適時に作る。サスティナブルな、本当のMADE IN JAPANを作りだします。全力で、ファッションを、アパレルを応援します」
事例2. 株式会社バンビ
節目の年の大きな変化
続いては、感動創造委員会 副委員長の舘林秀朗さんが代表を務める株式会社バンビさんです。
台東区御徒町に本社を構えるバンビさんは1930年創業、90年の歴史を持つメーカーです。
国内に4社5拠点を構え、国内で400名、香港と中国で5社5拠点1000名で運営しています。
主力は皮と金属両方の時計ベルト、皮小物やジュエリーの製造と卸売です。
2018年に舘林さんが代表取締役に就任され、2019年には増収増益を果たし、2020年は増産あるいは新しい事業のスタート、さらに90周年ということで記念の企画が様々計画されていました。
ところが2020年早々から中国で感染が拡大、日本国内においても顧客の販売自粛、休業によって感染拡大防止策と事業活動継続策に集中することになりました。
特に中国の拠点においては大きな問題でしたが、以前SARS感染症が猛威を振るった時に現場を指揮した役員がいたことで、とても素早く行動ができ、わずか3週間で操業再開させることができたということです。
経営者の精進
市場は緊急事態宣言によって停滞したことで、バンビさんの売上も前年と比べて大幅にダウンすることになりました。
しかし、社員さんの給料を9割保証するなど、経費を大きく縮小させることはしませんでした。
舘林さん曰く、これはこれまでの堅実経営のおかげであり、また「身の丈」にあった経営が社風としてあったことが現在のような緊急事態でも耐えうることができる要因になっているということでした。
また、会社を完全に止めることはせず、関係する企業に配慮して工場を稼働し続けてきました。
さらに、これを機にこれまで考えていた新しい事業や「持続可能モデル」への転換に向けて、現在の市場や顧客の構成比の見直しを図っているということです。
「最大の敵はウイルスではなく、心の中にある悪魔」
という『サピエンス全史』の著者であるユヴァル・ノア・ハラリ氏の言葉を引用して、現在ある問題は今突然起こったものではなく以前からあったもので、改めて問題視することではないと舘林さんは言います。
今回の困難は、会社の体制や課題、自分の実行力や心の弱さが表面化したもの。
それらの問題に自己や自社の能力を活かしてしっかり取り組む、できるだけ周囲と情報共有し協力し合う。判断するときは人や社会、次世代のことも考える。心穏やかに、安らかに、温かく調え、心のウイルスの増殖を抑え、周りの人に優しく、経営によって会社を強くして社員さんや顧客、取引先を豊かにしていきたい。
自分の心の中を平穏でいられるよう、そして冷静に判断ができることが今経営者に求められていることだということでした。
事例3. 湖楽おんやど富士吟景
最後に人気の温泉宿「富士吟景」の女将さんである外川由理さんです。
山梨県の富士河口湖温泉郷の宿で、その宿からの絶景で高い人気を誇り、予約の取れない宿として有名でした。
そんな富士吟景さんですが4月から休業を余儀なくされ、この6月も営業ができていません。
特に地方の観光地においては感染者を出してしまうと地域全体に影響を与えてしまうことから、地域内での同調圧力が激しいと外川さんは言います。
そんな中、売り上げ収入がゼロの状態であるにもかかわらず、役員報酬を最低限にまで下げて社員さんの給料を全額払っているということ。
それには訳があり、社員さんは社歴が長い人が多く、給料が下がると家計を直撃し大変なことになってしまうからだということです。
そのため、多額の借り入れをし、それでも無ければ自分たちの家を売ってでも社員さんの生活を守ると言います。
一方、社員さんはとにかく働きたい一心で会社に伝えてきたことから、自粛緩和されたタイミングで営業を再開することになりました(6月19日)。
ただし予約の人数は30人と、こちらもこれまでになかった少人数での再スタートとなった訳ですが、外川さんは「まさに初心に戻った」と言います。
これまでは365日完全満室でやってきたことを考えると、これまでがどれほど有難いことだったのかを再認識することができました。
お客様へのサービスも、「接触しないことがサービス」というこれまでとはまるで違うやり方に、戸惑いながらも一からサービスの方法を考えるという本当に新鮮な気持ちで仕事に取り組もうとしているということです。
同時に、仕事ができる喜び、こんな時でも来て頂けるお客様がいることが本当に幸せなことだと感謝していました。
まとめ
最後にファシリテーターをされた松井洋治さんから今回の発表のまとめをしてもらいました。
マルチョウさんについて特筆すべきは「意思決定の早さ」です。
この意思決定の早さは、「地域に役立ちたい」というビジョンを持っていたことが行動の原点になっています。
この「共通の目的」が明確になったことで社員さんの「貢献意欲」を引き出し、コミュニケーションにつなげていったことが大きな成果につながりました。
バンビさんは、先代までの内部留保を如何に役立てていくかということが大きなポイントであり、これは永続企業の特徴です。
内部留保は経営者自らが日々の鍛錬、精進をすることによって、状況に惑わされることなく、環境に応じて変化・行動をしていくことで生まれ、その精神が引き継がれることによって積み上げられていく。
代々の経営者が先代までの経営者に感謝し、同じように精進することで正しい意思決定ができる。
富士吟景さんについては、大人気の宿が突然ゼロになるという急転直下の状況、さらに地域におけるシビアな環境下において、決断を誤ると大変なことになってしまうが、休業することで地域を守り、多額の借り入れを決断して社員さんを守るという決断をされた。
これも普段の経営者の努力、精進によって出された意思決定であり、見習わなければならないところです。
長谷川剛さん、舘林秀朗さん、外川由理さん、大変な時期にとても貴重な事例発表ありがとうございました。
また、参加くださった皆様にも改めて感謝申し上げます。